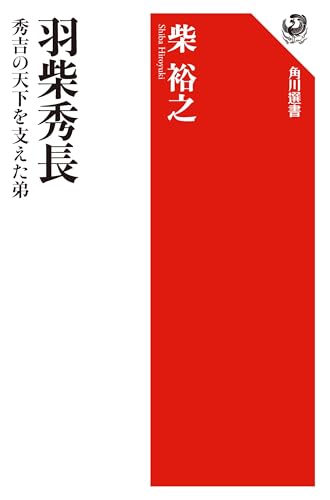豊臣秀次とその兄弟たちについて
豊臣秀次とは
豊臣秀次(とよとみひでつぐ)(1564~1595年)とは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で登場する豊臣秀吉(池松壮亮)・豊臣秀長(仲野太賀)兄弟の甥で、とも(宮澤エマ)にあたる瑞竜院殿日秀尼の長男です。
秀吉から1591(天正19)年12月28日に関白職と豊臣家の家督を譲られるも、秀吉の命令によって1595(文禄4)年7月15日に紀州の高野山において切腹を果たした人物としても知られています。
瑞竜院殿日秀尼の子供たちについて
瑞竜院殿日秀尼は長男・秀次以外にも次男・豊臣秀勝(1568~1592年)、三男・豊臣秀保(1579~1595年)を育てています。秀次にしてみると弟が2人いたということになります。
ただし次男・豊臣秀勝については瑞竜院殿日秀尼と三好吉房の間にできた子供であると考えられていますが、三男・豊臣秀保は日秀尼が46才のときに生まれた子供であることから、実子ではなく養子であるという指摘があります。
長男: 豊臣秀次(とよとみひでつぐ)
豊臣秀次の生年と名前について
豊臣秀次の生年について
大河ドラマ「豊臣兄弟!」で時代考証を担当されている黒田基樹さんの著作「羽柴秀吉とその一族」は、秀次の誕生年には諸説があり、主に「1564(永禄7)年」・「1565(永禄8)年」・「1567(永禄10)年」・「1568(永禄11)年」の4つの説があることを指摘しています。
「羽柴秀吉とその一族」の169ページから171ページにかけて、諸説の依拠するところを詳しく解説し、著者の黒田基樹さんは、秀次の誕生年として可能性が高い説は「1564(永禄7)年説」あるい「1565(永禄8)年説」と説明されています。
そのため今回の記事では豊臣秀次が誕生した年は「1564(永禄7)年」としています。
豊臣秀次の名前
豊臣秀次の幼名は、万丸(よろずまる)・治兵衛(じへえ)・次兵衛(じへえ)と言われることもありますが、しかし「豊臣秀次 「殺生関白」の悲劇」によると、豊臣秀次が名乗っていた幼名には確かな根拠はないと説明しています。
また豊臣秀次は1571(元亀2)年ごろから1584年3月まで、宮部継潤や三好康長の養子へ出されていたため、「宮部次兵衛尉吉継(みやべじへえのじょうよしつぐ)」や「三好孫七郎信吉(みよしまごしちろうのぶよし)」と名乗っていた時期があります。
豊臣秀次がどのように名前を変えていったかについては、「豊臣秀次 年表 誕生から「豊臣秀次切腹事件」に至るまで」という記事の「豊臣秀次の名前の変遷」を参考にしてください。
豊臣秀次の領地
豊臣秀次の領地としてはっきりしているのは、1585(天正13)年閏8月22日から1590年(天正18)年7月ごろまで治めていた近江国八幡山43万石と、1590年(天正18)年7月ごろから転封となった尾張国57万石です。
また秀次が尾張国に加増転封となった際、秀次の家臣たちは三河・遠江・駿河などの東海地方に所領を持つことになりました。そのため秀次は尾張に加えて東海地方の国々を合計して120万石の領地を管轄することになります。
豊臣秀次の業績
1571(元亀2)年ごろから1582(天正10)年にかけて豊臣秀次は、浅井長政の家臣であった宮部継潤の養子に出されています。
当時の木下秀吉(のちの豊臣秀吉)は宮部継潤を浅井家から織田家に味方につけるための寝返り工作を図っていました。そのため当時の秀次は「養子」と言うよりも、実質的には宮部継潤の安全を保証するための「人質」です。
のちに秀吉が浅井家を殲滅し、その功で北近江12万石の大名になったことを考えると、秀次は秀吉の大出世の「貢献者」とも「犠牲者」とも言えるでしょう。
また豊臣秀次は豊臣秀吉の天下統一事業のため、小牧長久手の戦い・紀州征伐・四国征伐・小田原征伐に従軍している一方で、茶の湯・連歌・書籍蒐集などの文芸政策にも明るく、当時の文化を保護することに貢献したと考えられています。
次男: 豊臣秀勝(とよとみひでかつ)
豊臣秀勝の名前について
豊臣秀勝の通称は「小吉(こきち)」で実名が「秀勝」とされています。「小吉」という通称が幼名としても使われていたかどうかは分かりません。
豊臣秀吉の身内には「秀勝」が3人いた
豊臣秀吉の親族を調べていると「秀勝」という実名を名乗った男性は3人いたことが分かっています。
| 名前 | 生年と死没年 | 説明 |
|---|---|---|
| 羽柴秀勝 (石松丸) | ?~1576年 | 秀吉の側室・南殿との間にできた実子 |
| 羽柴秀勝 (於次丸) | 1568~1585年 | 元は織田信長の五男で秀吉・寧々夫妻の養子 |
| 豊臣秀勝 (小吉) | 1568~1592年 | 瑞竜院殿日秀尼と三好吉房の次男 |
このため豊臣秀勝は他の秀勝と区別するために、現代では「小吉秀勝(こきちひでかつ)」と呼ばれることがあります。
なお「3人の秀勝」を比較するために「秀勝 3人 羽柴秀勝(石松丸) 羽柴秀勝(於次丸) 豊臣秀勝(小吉)」という関連記事も公開しています。合わせて参考にしてください。
豊臣秀勝の領地
豊臣秀勝は最初、近江勢田(現在の滋賀県大津市)に加えて、摂津安岡寺・摂津富田宿久(いずれも現在の大阪府高槻市)などに所領があったと考えられています。
1585(天正13)年12月10日、丹波亀山(現在の京都府亀山市)の領国大名であった秀吉の養子・羽柴秀勝(於次丸)が亡くなります。このとき豊臣秀勝(小吉)が代わって丹波亀山28万石に入国。
しかし秀勝は丹波亀山の領地高が少ないと叔父・秀吉に不満を訴えると逆に秀吉の怒りを買い、1589(天正17)年7月に美濃国大柿に所領を変えられて、領地高は5万6,000石に減封。
もっとも1590(天正18)年の小田原征伐で戦功があったとして、甲斐一国22万石に加増転封。しかし秀勝による甲斐国の統治は7ヶ月で終わり、美濃国岐阜13万3,000石に所領を替えられます。
甲斐一国から岐阜への転封は、日秀尼が秀吉に対して「甲斐は都から遠すぎるから近くの領地にしてやってほしい」と言う願いが通ったものとも言われています。
豊臣秀勝の業績
本人の都合や母親の要望でコロコロと所領が変わったように見える豊臣秀勝ですが、1585年には丹波亀山で28万石の領地を与えられています。
このことから豊臣一門衆の大名として豊臣秀勝の序列は、豊臣秀長(大和国・紀伊国・和泉国100万石。実質的には73万石)・豊臣秀次(近江八幡山43万石)に次ぐ第3位の地位を占めていたと考えられます。
また豊臣秀勝は浅井長政の三女である江(ごう)と結婚し、完子(さだこ)という女の子をもうけ、豊臣家の血筋を長く残したとも言えるでしょう。
三男: 豊臣秀保(とよとみひでやす)
豊臣秀保の名前について
豊臣秀保の幼名は「鍋丸(なべまる)」と伝えられています。
その一方で1588(天正16)年に行われた後陽成天皇と正親町上皇による聚楽第行幸には「御虎侍従」と名前が記録されていることから、秀保の幼名を「御虎(おとら)」とする説もあります。
豊臣秀保の領地
豊臣秀保は1588(天正16)年1月に叔父・豊臣秀長の養嗣子に迎えられ、1591(天正19)年1月21日に秀長が病死した後、その遺領を引き継ぎます。
ただし秀保が秀長からの相続が認められた国は大和と紀伊の2カ国で、実質的な領地高は59万石程度であったと考えられます。
豊臣秀保の業績
豊臣秀保の業績といえば、なんと言っても「天下一の補佐役」と言われた豊臣秀長の後継者となったことでしょう。しかしその秀保も1594(文禄3)年4月16日にわずか16才で病死。
秀保は妻はいたものの、秀保が病死した時点で8才に過ぎなかったため、後継者をもうけることはできませんでした。そのため「大和大納言家」と呼ばれた豊臣秀長の家系は、秀長・秀保の二代で途絶えることなりました。
豊臣秀次 兄弟 関連記事と参考書籍
豊臣秀次 兄弟 関連記事
瑞竜院殿日秀尼の3人の子供たちである、豊臣秀次・豊臣秀勝・豊臣秀保の概略については以下の記事においてそれぞれ紹介しています。
豊臣秀次 兄弟 参考書籍
今回の記事を書くにあたって以下の文献を参考にしました。柴裕之さんと黒田基樹さんは、いずれも2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で時代考証を担当されています。