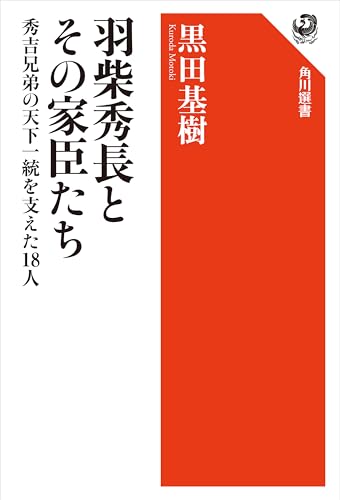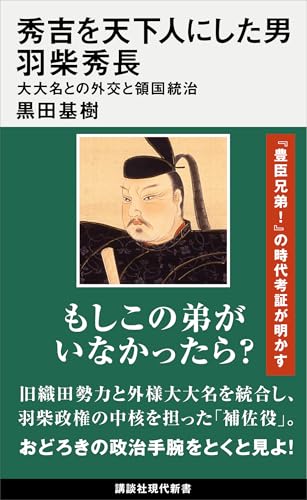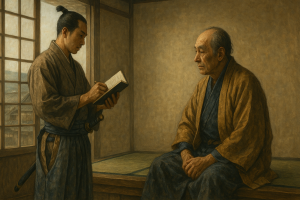宇多頼忠の名前について
宇多頼忠とは
宇多頼忠(うだよりただ)(?~1600年)とは旧名を「尾藤頼忠(びとうよりただ)」と言い、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主人公・豊臣秀長(仲野太賀)の家臣の1人です。
宇多頼忠は紀伊国有田郡にあった広城(ひろじょう)(現在の和歌山県広川町)の城主を任されたり、1586(天正14)年の熊野地域の攻略に参加していたことから、豊臣秀長からはとりわけ紀州南部にある熊野地方の統治を任された人物であると考えられています。
宇多頼忠の名前
「宇多頼忠」と言う名前は苗字を変更したのちの名前で、当初は「尾藤(びとう)」という苗字を使い、「尾藤二郎三郎」を名乗っていました。
「羽柴秀長とその家臣たち」によると「二郎三郎(じろうさぶろう)」は仮名(けみょう)で、通称は久右衛門尉(きゅうえもんのじょう)だったようです。
さらに宇多頼忠は、1588(天正16)年に豊臣秀長の諸大夫家臣として従五位下下野守に任じられていることから、「下野守」と言う受領名も持っています。
「諸大夫家臣」とは
「諸大夫家臣」とは公卿である豊臣秀長(従二位権大納言)が宮中に参内するときに御所の中まで随伴することができる家来のことです。
秀長に随伴するほとんどの家来は御所の外までしか警護できないのに対して、「諸大夫家臣」は従五位下の官位を持ち、宮中には昇殿できないものの御所の中に入って警護することが許されていました。
宇多頼忠の出自と家族
宇多頼忠の出自
「羽柴秀長とその家臣たち」によると明確な出自は判明しないものの、「竹生島奉加帳」の1576(天正4)年の記述から「尾藤二郎三郎」の存在が認められ、「尾藤知宣」と同時に見えていることから、2人は兄弟の関係があると指摘しています。
また同時に同書では尾藤知宣・頼忠兄弟は、織田家直臣の尾藤源内の子供であった可能性が高いとしています。
宇多頼忠の家族
上述したように宇多頼忠の父は尾藤源内。兄弟には知宣の他に長兄の又八がいました。
子供は「河内守」と呼ばれた頼次と、「皎月院(こうげついん)」と考えられる娘がおり、その娘は石田三成に嫁ぎ、嫡男・石田重家をもうけています。つまり宇多頼忠は石田三成の義理の父にあたるのです。
秀長家臣としての宇多頼忠の動向
秀吉から秀長の直臣に転じる
宇多頼忠は元は豊臣秀吉の直臣でした。豊臣秀長の直臣に転じた時期についてはっきりとは分からないものの、1584(天正12)年10月までには秀長の直臣になったことがうかがわれます。
このとき秀長は秀吉の直臣であった尾藤知宣から近江土田(現在の滋賀県多賀町)に向けて軍勢派遣の要請を受け、藤堂高虎と宇多頼忠(当時は尾藤頼忠)を派遣しています。
紀伊国有田郡の広城城主に
その後、1585(天正13)年3月から行われた紀州征伐において、頼忠も軍勢を率いて出陣。同年4月には和歌山城の支城とも言える、紀伊国有田郡にあった広城に配置。
頼忠が広城に配置された直後の所領高は判明していないものの、のちに記された「伏見普請役之帳」から頼忠の所領は1万3,000石程度であったと推測されます。
紀州熊野地方の制圧に従軍
秀吉・秀長兄弟による紀州征伐が1585(天正13)年3月に行われ、紀伊一国は秀長の領国とされたたものの、熊野地方を中心とした紀州南部の地域は完全掌握と言うには程遠い状態でした。
そのため1586(天正14)年9月から1589(天正17)年4月にかけて、頼忠は桑山重晴・青木重吉・杉若無心・藤堂高虎といった秀長の重臣・与力らとともに紀伊熊野地方の攻略に従軍。
熊野地方の北山地域の検地を行ったのは秀長死後のこと
熊野地方の中でも特に北山地域は最後まで秀長の統治に抵抗し、豊臣政権の支配の象徴である「太閤検地」が実施できたのは、1591年1月(天正19)年に秀長が亡くなったのちのことでした。
つまり宇多頼忠が配置された当時の紀州南部はそれだけ武家が治めることが難しかったことを示していたことになります。
ちなみに熊野地方の北山地域は、現在の和歌山県北山村に相当します。北山村は現代の日本では唯一の「飛び地の村」として知られ、和歌山県にある他の自治体とはどことも隣接していません。
従五位下下野守を授爵
こうした「難治の地」である紀州南部の最前線の1つを任された頼忠は、秀長の「諸大夫家臣」として朝廷から従五位下下野守の官職を授けらています。
1588(天正16)年に毛利輝元が大和郡山城を訪問した際には進物が贈られ、「尾藤下野守」と言う記録が残されています。
もちろん頼忠の授爵は豊臣秀吉・秀長兄弟の推挙に基づくものでしょう。それだけ頼忠は秀長から信頼されていたということになります。
秀長死後の宇多頼忠の動向
苗字を「尾藤」から「宇多(宇田)」に改称
1591(天正19)年1月21日、豊臣秀長が大和郡山城で病死。後継者はかねてから養嗣子として指名されていた豊臣秀保です。
代替わりをしたのちも、頼忠は引き続き秀保に仕えます。ただ秀保治世の時代に頼忠は苗字をそれまでの「尾藤」から「宇多(または宇田)」に改めています。
改称した時期や理由ははっきりしないものの、1592(文禄元)年には改称した苗字が史料の中で見られています。
なお一般的には、兄知宣が秀吉から処罰され、天正十八年に処刑されたことをうけて、秀長が苗字の改称を認めたとされているが、明確な根拠はみられていない。また改称した苗字について、妻方の苗字とする見解もみられているが、これについても明確な根拠はみられていない。それらの伝承の出所を確認していく必要があるだろう。
黒田 基樹. 羽柴秀長とその家臣たち 秀吉兄弟の天下一統を支えた18人 (角川選書) (pp. 156). (Function). Kindle Edition.
秀保死去後の宇多頼忠の動向
豊臣秀保は1595(文禄5)年3月ごろから病気を患うようになり、大和国の十津川で療養をしていましたが、同年4月16日に死去。秀長・秀保の二代に渡って続いた「大和大納言家」は断絶することになります。
ただ秀保が死去したのちの宇多頼忠は再び豊臣秀吉の直臣となり、紀州の所領はそのまま安堵。1598(慶長3)年には家督を嫡男の頼次に譲ります。
しかし1600(慶長5)年の関ヶ原の戦いでは石田三成率いる西軍に味方し、三成の本拠地である近江佐和山城を守備。同年9月18日に佐和山城の落城に伴い、宇多頼忠は戦死したと考えられています。
宇多頼忠 関連記事と参考文献
宇多頼忠 関連記事
豊臣秀長のもとで紀州の支配と統治に尽力した宇多頼忠に関しては以下の記事でも言及しています。合わせて参考にしてください。
宇多頼忠 参考文献
今回の記事を書くにあたって以下の文献を参考にしました。著者の黒田基樹さんは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で時代考証を担当されています。