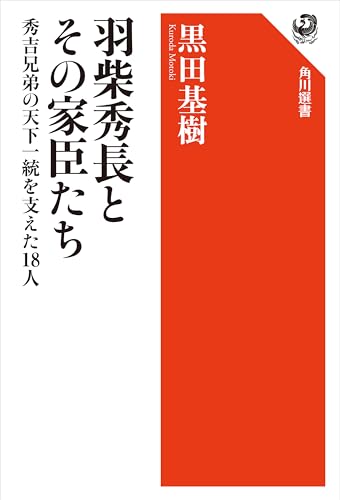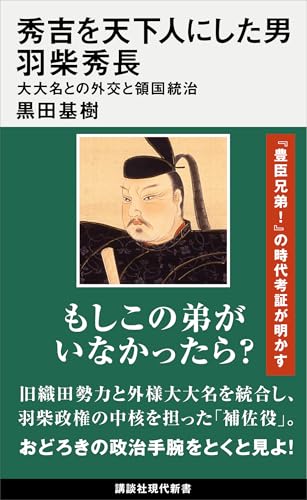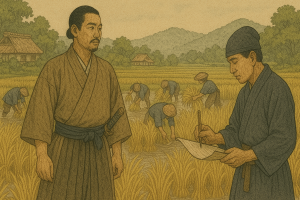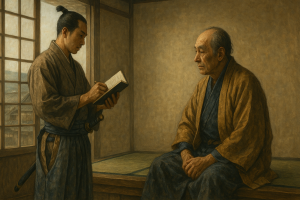桑山重晴の名前について
桑山重晴とは
桑山重晴(くわやましげはる)(1524~1606年)とは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主人公・豊臣秀長(仲野太賀)の家臣の1人です。
桑山重晴はもともと豊臣秀吉の直臣でしたが、1583(天正11)年3月ごろまでには秀長の直臣に転向。秀長の領国とされた和泉・紀伊において、それぞれの国の要衝となる岸和田城の城代と和歌山城の城代を務めた秀長家中の筆頭家老です。
さらに桑山重晴は、秀長が従軍する戦いにおいて常に別働隊か先陣の大将を務めてきたことも知られています。
桑山重晴の名前について
桑山重晴の最初の実名は「重勝」でのちに「重晴」と改名。
また通称として「修理進(しゅりのしん)」・「修理亮(しゅりのすけ)」・「修理大夫(しゅりのたいふ)」・「治部卿法印(じぶのきょうほういん)」。
さらに1593(文禄2)年に出家をしたのちは「宗栄(そうえい)」と言う出家名を用いています。
桑山重晴の官途名
桑山重晴は、藤堂高虎・羽田正親・杉若無心・福智長通らと同じく、豊臣秀長の「諸大夫家臣」の1人です。「諸大夫家臣」とは公卿である秀長(従二位権大納言)が、宮中に参内するときに御所の中まで随伴することができる家来のことです。
秀長に随伴するほとんどの家来は御所の外までしか警護できないのに対して、「諸大夫家臣」は従五位下の官位を持ち、宮中には昇殿できないものの御所の中に入って警護することが許されていました。
桑山重晴は秀長の「諸大夫家臣」として「修理大夫(しゅりのたいふ)」と言う官途名を持っていたとされています。
桑山重晴の出自と家族
桑山重晴の出自
桑山重晴の出自はあまりはっきりしていません。重晴の父は尾張国の住人であったと見られています。
桑山重晴の家族
桑山重晴の子供として長男・一重と三男の元晴が知られています。さらに一重の子・一晴は重晴の嫡孫にあたり、桑山本家の家督を譲られています。
秀長家臣としての桑山重晴の役割
桑山重晴の戦歴について
冒頭で述べたとおり桑山重晴は秀長家臣として秀長が参加する数々の戦に従軍し、その別働隊あるいは先陣の大将を務めてきました。
「羽柴秀長とその家臣たち」で説明されている桑山重晴の戦歴を表にすると以下の通りです。
| 西暦(和暦) | 出来事 |
|---|---|
| 1583(天正11)年 | 賤ヶ岳の戦い。秀長軍の別働隊として近江賤ヶ岳の頂上に布陣 |
| 1584(天正12)年 | 小牧長久手の戦い。秀長軍の別働隊として紀伊新宮の堀内氏善を攻撃 |
| 1585(天正13)年9月 | 紀伊熊野攻め。青木重吉・杉若無心・宇多頼忠(尾藤頼忠)・藤堂高虎とともに紀伊田辺まで進軍 |
| 1587(天正15)年4月21日 | 九州征伐。秀長軍の部将として日向国にある島津方の諸城を受け取り |
| 1587(天正15)年5月8日 | 九州征伐。島津義珍(義弘)への降伏勧告 |
| 1587(天正15)年5月13日 | 九州征伐。秀長軍の先陣として福智長通とともに日向高原まで進軍 |
島津義久・義弘兄弟に対する「取次」を担当
「天下一の補佐役」と言われた豊臣秀長は、豊臣政権を取り巻く外様の大大名(徳川家康・毛利輝元・長宗我部盛親)などとコネクションを持っており、彼らに対して「取次(外交や外交事務のこと)」や「指南(政治指導や軍事指導のこと)」を行なっていました。
福智はこの時、高原まで進軍していたことがわかる。秀長に先行して飯野城への進軍をすすめていたとみられる。またこうした経緯から、秀長の家老では、義弘への取次は、福智長通と桑山重晴が担ったことがわかる。
黒田基樹. 秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治 (講談社現代新書) (p. 88). (Function). Kindle Edition.
このことに伴い秀長の諸大夫家臣たちもどこかの外様大名の「取次」を務めており、桑山重晴の場合、九州征伐の経緯から、福智長通とともにもっぱら島津義久や島津義弘の「取次」を務めていたとみなされています。
城代として和泉・紀伊を統治
こうした戦歴の最中に豊臣秀長は領国を但馬国と播磨国の3郡(多可郡・加東郡・飾東郡)から、和泉・紀伊・大和の3カ国に移し、最終的には大和郡山城を本拠地とします。
筆頭家老としての桑山重晴の役割は、秀長が本拠地としなかった領国の和泉・紀伊において要衝となる地を治めることです。
そのために和泉では岸和田城代に、紀伊では和歌山城代に任命され、紀州の地において3万2,000石の領地を有していたと言われています。
秀長死後の桑山重晴の動向
秀長の死後は後継者・豊臣秀保に仕える
1591(天正19)年1月21日、豊臣秀長が大和郡山城で病死。後継者はかねてから養嗣子として指名されていた豊臣秀保です。
代替わりをしたのちも、桑山重晴は引き続き秀保に仕えます。1591(天正19)年2月13日、豊臣秀保・「秀保の妻」・慈雲院が上洛するに伴い、それに随行した羽田正親に対して、秋篠伝左衛門尉と相談しながら秀吉に対応するよう助言したことが明らかになっています。
さらに1592(文禄元)年の朝鮮出兵(文禄の役)では、桑山重晴自身は出兵こそしなかったものの、一族で嫡孫の桑山一晴(小藤太)らが、藤堂高虎や紀伊国の国衆たちとともに朝鮮へ渡海しています。
秀長の家系が断絶したのちの桑山重晴の動向
豊臣秀保の死去ののち再び秀吉に仕える
豊臣秀保は1595(文禄5)年3月ごろから病気を患うようになり、大和国の十津川で療養をしていましたが、同年4月16日に死去。秀長・秀保の二代に渡って続いた「大和大納言家」は断絶することになります。
ただ秀保が死去したのちの桑山重晴は再び豊臣秀吉の直臣となり、紀州の所領は安堵の上、和泉国で1万石を加増。
関ヶ原の戦いでは東軍に味方
1600(慶長5)年の関ヶ原の戦いにおいて、桑山重晴は徳川家康が率いる東軍に味方。
戦後に隠居して嫡孫・一晴に家督を譲ります。そのさい紀伊の所領を一晴と重晴の三男である元晴に分知して、自らは和泉の所領を領有したと考えられています。またこれらのうち桑山一晴は大和新庄藩の初代藩主となります。
その後、桑山重晴は1606(慶長11)年に83才で死去。
桑山重晴 関連記事と参考文献
桑山重晴 関連記事
豊臣秀長の筆頭家老である桑山重晴に関しては以下の記事でも言及しています。合わせて参考にしてください。
桑山重晴 参考文献
今回の記事を書くにあたって以下の文献を参考にしました。著者の黒田基樹さんは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で時代考証を担当されています。