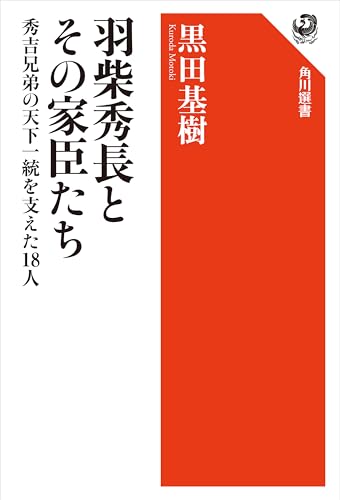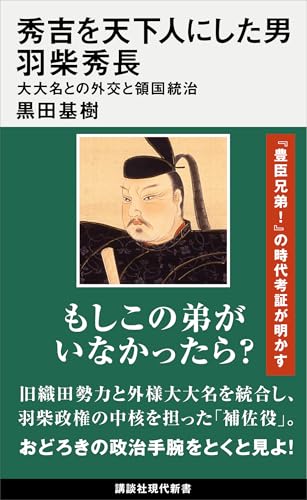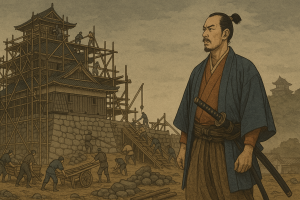藤堂高虎の名前について
藤堂高虎とは
2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で佳久創さんが演じる藤堂高虎(1556〜1630年)とは、豊臣秀長(仲野太賀)の家臣の1人です。
藤堂高虎が豊臣秀長に仕えていたときは、「大和大納言家」と呼ばれた家中の中で主に軍事と外交を担当。紀伊国粉河をはじめとして2万石の領地を有していました。
藤堂高虎はのちに行われた関ヶ原の戦い(1600年)において徳川家康が率いる東軍に味方。その戦功により明治時代初期の廃藩置県まで続く伊勢津藩の初代藩主となり、豊臣秀長の家臣だった者として最も出世した戦国武将となりました。
藤堂高虎の名前について
藤堂高虎の仮名(けみょう)は「与吉(よきち)」で、1576(天正4)年に通称を「与右衛門尉(よえもんのじょう)」に改称。
1588(天正16)年4月には朝廷から従五位下佐渡守に叙任されたことから、受領名は「佐渡守(さどのかみ)」となります(のちに「和泉守」に変更)。
藤堂高虎の出自と家族
藤堂高虎の出自
藤堂高虎は北近江に領地を有していた戦国大名の浅井長政の家臣・藤堂虎高の次男として、近江国犬上郡藤堂村で誕生。
浅井長政に仕えていたときの藤堂家の身分は高くはなく、津市の説明によると半農半兵の郷士か、あるいは足軽程度であったと考えられます。
藤堂高虎が豊臣秀長に仕えるまで
もともとは浅井家の家臣であった藤堂高虎は、阿閉貞征(あつじさだゆき)・磯野員昌(いそのかずまさ)・織田信澄(おだのぶずみ)と主君を変え、20才のときに知行300石で豊臣秀長(当時は木下小一郎長秀)に仕官しました。
| 西暦(和暦) | 年齢(満年齢) | 出来事 |
|---|---|---|
| 1556(弘治2)年 | 0才 | 近江国犬上郡藤堂村で藤堂虎高の次男として生まれる |
| 1570(元亀元)年 | 14才 | 浅井氏に仕える。姉川の戦いで初陣を飾る。 |
| 1572(元亀3)年 | 16才 | 浅井家を出奔。阿閉貞征に仕官 |
| 1573(天正元)年 | 17才 | 阿閉家を出奔。磯野員昌に80石で仕える。 |
| 1574(天正2)年 | 18才 | 磯野員昌が織田信澄の家臣になったことに伴い信澄の家臣に |
| 1576(天正4)年 | 20才 | 秀長に乞われて300石で仕官 |
藤堂高虎の家族
藤堂高虎の家族として知られている人物は祖父の藤堂忠高と父の藤堂虎高、兄として源七郎高則、養子として迎えた一高(のちに高吉)、嫡男の高次、次男の高重などが知られています。
秀長家臣としての藤堂高虎の役割
常に秀長軍の先鋒を引き受けた藤堂高虎
秀長の家臣として藤堂高虎が担った役割の1つが軍事活動で、それも数々の戦いにおいて先鋒を務めており、文字通り「戦国武将」をイメージさせる人物であったと言えるでしょう。
高虎は秀長死後に朝鮮出兵や関ヶ原の戦いに参加することがよく知られていますが、秀長家臣時代のときだけでも数多くの戦に出陣していることが分かっています。
「羽柴秀長とその家臣たち」の記述を元に秀長の家臣としての藤堂高虎が出陣した戦いを年表形式にすると以下の通りです。
藤堂高虎はまさしく「歴戦の勇者」であり、数々の武功を立てわずか300石の知行から2万石の大名にまで駆け上がりました。
| 西暦(和暦) | 年齢(満年齢) | 出来事 |
|---|---|---|
| 1580(天正8)年 | 24才 | 但馬国七美郡で一揆鎮圧 |
| 1581(天正9)年 | 25才 | 秀長の因幡進攻に従軍 |
| 1582(天正10)年3月 | 26才 | 秀吉の備中進攻に従軍。冠山城・高松城攻めに戦功を挙げる |
| 1582(天正10)年6月 | 27才 | 山崎合戦。秀長軍の先陣として勝竜寺城を攻撃 |
| 1583(天正11)年 | 27才 | 賤ヶ岳の戦い。越前丸岡城攻めで戦功を挙げる |
| 1584年(天正12)年 | 28才 | 小牧長久手の戦い。伊勢松ヶ島城攻めで戦功 |
| 1585年(天正13)年3月 | 29才 | 紀州征伐に出陣。紀伊田辺まで進軍 |
| 1585年(天正13)年5月 | 29才 | 四国征伐に出陣。阿波木津城と一宮城の攻略。同年7月に長宗我部元親を降伏させる |
| 1585年(天正13)年9月 | 29才 | 宇多頼忠(尾藤頼忠)・杉若無心・青木重吉とともに紀伊熊野攻め。敵軍の大将を討ち取る |
| 1587年(天正15)年4月 | 31才 | 九州征伐に出陣。「根白坂の戦い」において宮部継潤を救出 |
| 1589年(天正17)年4月 | 33才 | 羽田正親とともに紀州熊野地方の北山地域に出陣 |
| 1590(天正18)年 | 34才 | 病気の秀長に代わって小田原征伐に出陣。伊豆韮山城の攻撃 |
「外交官」としての藤堂高虎 徳川家康との外交を担当
藤堂高虎は戦に強かっただけでなく「築城の名人」や「算術の名人」といった側面もありましたが、秀長家臣としての藤堂高虎は家中において外交の役割も担っていました。
豊臣秀長は徳川家康や毛利輝元をはじめとした、豊臣政権から見た外様の大大名のほとんどに「指南(政治指導や軍事指導のこと)」を行っており、そのうち一部の大名に対して藤堂高虎は「取次(外交や外交事務のこと)」の担当していました。
藤堂高虎が「取次」をしたと考えられる外様の大大名とは以下の通りです。
- 長宗我部元親
- 大友宗滴
- 毛利輝元
- 徳川家康
例えば、1586(天正14)年、徳川家康は豊臣秀吉に臣従を誓ったのち、京・聚楽第に屋敷を構えることになりますが、そのとき徳川屋敷の普請を担当したのは藤堂高虎でした。こうした高虎から家康の助力は、「取次」の一環として考えられます。
こうした秀長家臣による外様大名に対する「取次」の活動は桑山重晴・羽田正親・福智長通・疋田就長にも共通して見られ、藤堂高虎も秀長家中の「外交官」として数えられていたことが分かるでしょう。
行政官としての藤堂高虎 豊臣家の熊野山奉行
意外なことかもしれませんが藤堂高虎には「行政官」としての側面もあります。
1588(天正16)年12月にそれまで紀州熊野地方で豊臣家の山奉行を務めていた吉川平助が材木の不正取引で罪に問われて斬首に処されたのち、その後任として羽田正親とともに藤堂高虎も熊野山奉行に就任。
熊野山奉行の任務は豊臣家のために熊野地方の木材を供給することで、藤堂高虎は羽田正親や、紀伊の田辺上野山城主の杉若無心とともに木材を京や大坂に送り出す役割も担っていました。
秀長死後の藤堂高虎の動向
秀長の死去後、後継者・豊臣秀保に仕える
1591(天正19)年1月21日、豊臣秀長が大和郡山城で病死。
後継者はかねてから養嗣子として指名されていた豊臣秀保です。藤堂高虎は引き続き豊臣秀保に仕え、秀長から預かった養嗣子の千丸を元服させ、藤堂一高(かつたか)と名乗らせます。
また1592(文禄元年)の朝鮮出兵(文禄の役)では、紀伊国の国衆(杉若氏宗など)たちとともに朝鮮に渡海。
秀保の死後に「高野山で出家」した逸話
しかし今度は豊臣秀保は1595(文禄5)年3月ごろから病気を患うようになり、大和国の十津川で療養をしていましたが、同年4月16日に死去。
このため秀長・秀保の二代に渡って続いた「大和大納言家」が断絶します。真偽は分かりませんが、このとき高虎は出家して高野山に遁世したという逸話が残されています。
文禄四年四月に秀保が死去すると、高虎は剃髪して紀伊高野山に遁世したという。秀保の死去により、大和羽柴家の断絶にともなう行動ということになっている。しかし大和羽柴家については、同年四月二十七日には、秀次の子によって継承させることが取り決められていたことが明らかになっている(村井祐樹『中世史料との邂逅』)。しかしこの取り決めは、同年七月の秀次事件によって消滅することになる。そのことを踏まえるならば、高虎の出家・遁世は創作か、あったとすれば秀保個人の死を悼み、その後の大和羽柴家の存続とは無関係に行われたことになる。
黒田 基樹. 羽柴秀長とその家臣たち 秀吉兄弟の天下一統を支えた18人 (角川選書) (pp. 58). (Function). Kindle Edition.
豊臣秀吉の直臣となり8万石の大名に出世
秀長・秀保の二代に渡って仕えていた家臣の多くがそうであったように、1595(文禄4)年には藤堂高虎も豊臣秀吉の直臣に転じます。
ただ藤堂高虎は杉若無心や横浜良慶(横浜一庵)などと異なり、秀吉から大きな加増を受け、紀伊粉河2万石から伊予宇和島7万石の領国大名に出世。
さらに朝鮮出兵(慶長の役)での戦功が認められ、伊予大洲で1万石がさらに加増され、知行高は8万石を数えるようになります。
徳川の治世には総石高32万3,000石の国持大名に
1600(慶長5)年の関ヶ原の戦いでにおいて、藤堂高虎は徳川家康率いる東軍に味方。戦功が認められ伊予今治12万石が加増。高虎の知行高は合計20万石に。
1608(慶長13)年には伊予に2万石の領地を残して、伊賀・伊勢22万石に転封。最初は伊賀上野城、のちに伊勢津城を本拠地とします。
さらに1625(寛永2)年には国持大名として従四位下侍従に叙任。山城・大和などで加増を受け、総石高は32万3,000石に。1630(寛永7)年10月5日に75才で死去します。
関ヶ原の戦いののちも秀長の菩提を弔い続けた藤堂高虎
藤堂高虎の後半生を見ると、豊臣家から徳川家に乗り換えてしまったイメージがあるかもしれません。
しかし高虎は秀長から受けた恩を決して忘れなかったと言えます。それは1607(慶長12)年に行われた秀長の十七回忌の法要は高虎の手によって行われているからです。
「羽柴秀長とその家臣たち」によると高虎は秀長の菩提者であることを引き受けたとみなすことできるとしています。
藤堂高虎 関連記事と参考文献
藤堂高虎 関連記事
豊臣秀長の家臣の中で最も出世したと言える藤堂高虎に関しては以下の記事でも言及しています。合わせて参考にしてください。
- 豊臣秀長の家臣 20人 小堀新介・藤堂高虎・桑山重晴・横浜良慶他
- 豊臣秀長 子供 千丸(仙丸)のちの藤堂高吉 秀長の最初の養嗣子
- 豊臣兄弟! 藤堂高虎(佳久創) 秀長の重臣の一人
- 豊臣秀長と藤堂高虎の関係とは 秀長と高虎の7つの逸話・エピソード
藤堂高虎 参考文献
今回の記事を書くにあたって以下の文献を参考にしました。著者の黒田基樹さんと編著者の柴裕之さんは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で時代考証を担当されています。
- 黒田基樹 羽柴秀長とその家臣たち 秀吉兄弟の天下一統を支えた18人 角川選書
- 黒田基樹 秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治 講談社現代新書
- 柴裕之編著「豊臣秀長 (シリーズ・織豊大名の研究)」戎光祥出版