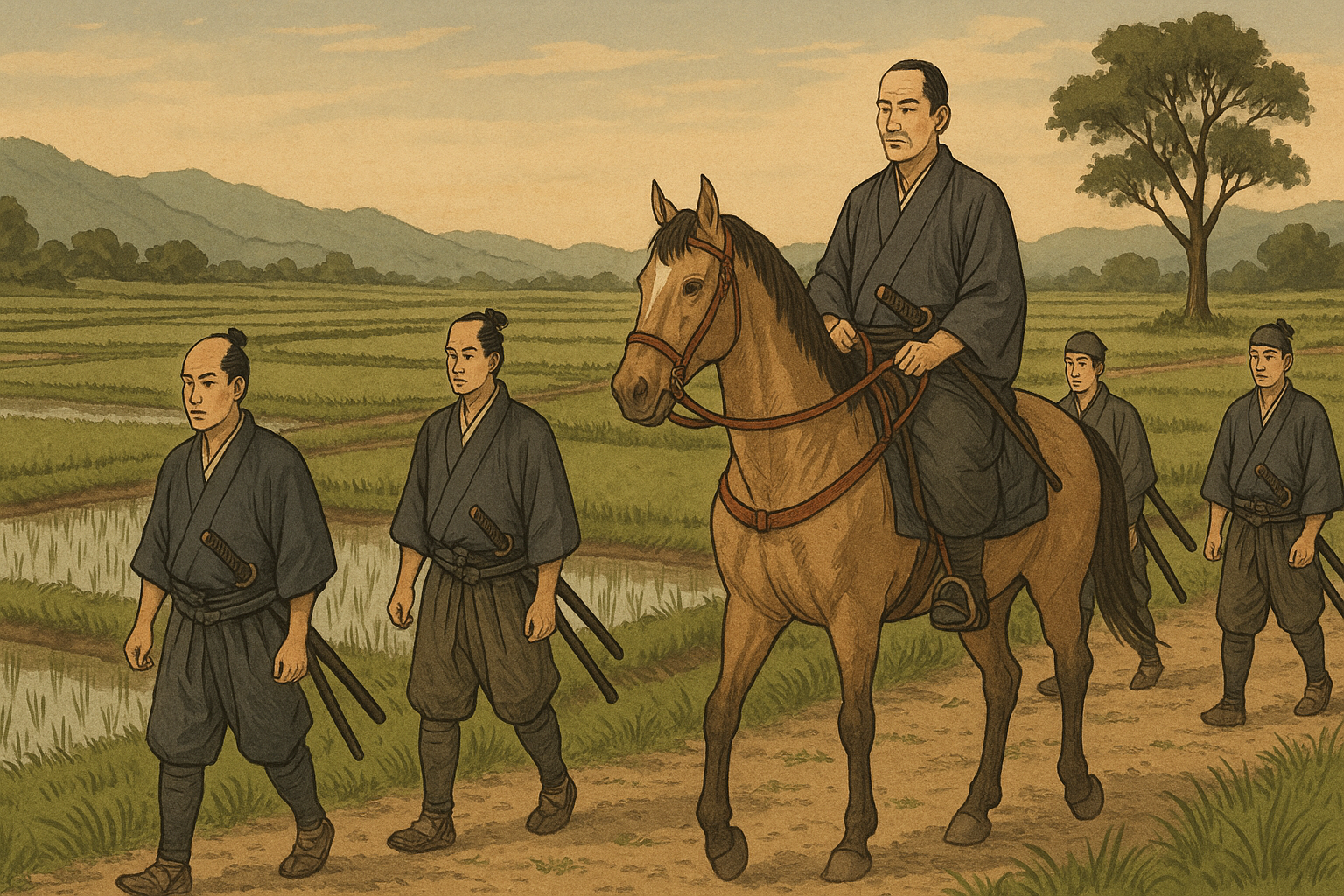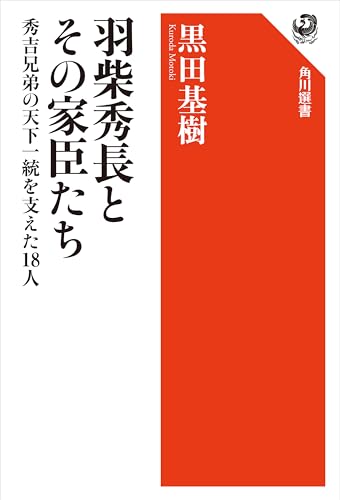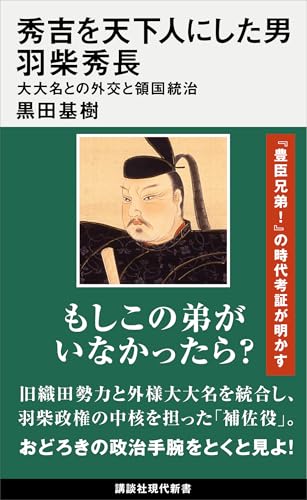羽田正親の名前について
羽田正親とは
羽田正親(はねだまさちか)(?~1595年)は、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主人公・豊臣秀長(仲野太賀)の家臣の1人で、大和小泉城主として大和国添下郡で4万8,000石の領地を有していました。
また羽田正親は「大和大納言家」と言われた豊臣秀長とその後継者・豊臣秀保の治世の時代には、和泉半国の行政、和歌山城の築城、徳川家康と小早川隆景の取次(外交)、大仏造営のために材木供給や紀伊国の木材管理などを担当。
その後秀保が亡くなり「大和大納言家」が断絶したのちは、豊臣秀次の家臣に。1595(文禄4)年に発生した「豊臣秀次切腹事件」に連座させられ越前北庄で切腹させられることになります。
羽田正親の名前について
「羽柴秀長とその家臣たち」によると、泉佐野市の史料で登場する名前は「はねたちうひやうへ(羽田忠兵衛)」。「高山公実録」に収録されている賤ヶ岳の合戦図に登場する名前は「羽田長門」です。
1585(天正13)年の四国征伐において秀長の与力に対して出した書状では「羽田忠右衛門尉」を通称していたことが分かっています。
また「毛利輝元上洛日記」の1588(天正16)年7月25日などいくつかの記述には「羽田長門守」と記されています。
名前に「長門守」がある意味
「毛利輝元上洛日記」の記述から秀長の家来の諸大夫(公卿が宮中に参内するときに御所の中にまで入ることができる家来)として、羽田正親は朝廷から「従五位下長門守」の官職が授けられていたことが分ります。
秀長の家来で諸大夫とされた家臣には他に藤堂高虎・桑山重晴・福智長通・杉若無心など数名がおり、羽田正親も秀長の有力な家臣の1人であったと言えるでしょう。
羽田正親の出自と家族について
羽田正親の出自
羽田正親は生年が不詳であるように、その出自は不明です。羽田正親が史料に初めて登場するのは上述した大阪府泉佐野市の史料で和泉国の一部地域を担当する代官に任じられたときです。
羽田正親の家族
「羽柴秀長とその家臣たち」では羽田正治という人物を紹介して正親の父か兄に当たる人物としていますが、人物の詳細は分かりません。
また1588(天正16)年9月に毛利輝元が大和郡山城を訪問したときには羽田正親の屋敷が宿所にあてられ、そのときの記録として正親の嫡男とみなされる「伝八」の存在が認められます。
秀長・秀保の家臣としての羽田正親の役割
和泉半国の行政と和歌山城の普請を担当
1585(天正13)年5月に豊臣秀長が和泉・紀伊の2カ国を領国としたことから、和泉国上二郡(大鳥郡と和泉郡)の代官を務めていたことが分かっています。
このことから秀長は正親に行政官としての役割を期待していたのでしょう。なお同時期には秀長家臣の藤堂高虎・横浜良慶(横浜一庵)とともに、和歌山城の普請も担当。
徳川家康・小早川隆景の「取次」を担当
「取次」という単語自体は、現代日本語の一般名詞としても使われますが、豊臣秀長の文脈で言うと「外交」や「外交事務」という単語に置き換えると意味が分かりやすくなります。
豊臣秀長は豊臣政権の周りに存在する徳川・毛利・長宗我部・島津など外様の大大名たちと太いコネクションを持っていましたが、羽田正親はその配下として徳川家康と小早川隆景の「外交事務」を担当していました。
徳川家康への取次例
1586(天正14)年ごろ徳川家康は方広寺大仏殿造営のために三河国の本證寺・勝鬘寺・上宮寺など一向宗を宗旨とする7つの寺に対して材木5,000本を調達するよう命じます。
しかしこれらの各寺はすでに諸役(上納金や労働力提供のこと)がすでに過重になっていることを理由として、家康の命令を拒否。一方家康はこれらの諸寺に三河国から退去するよう命令。
そのことを聞きつけた秀長は、家康と各寺の本山である本願寺の下間頼廉の間に立ち調停を開始。これらの寺に課されている木材以外の諸役を免除することとし、一向宗徒たちが三河国から追い出されることを食い止めます。
このとき家康と下間頼廉に対する「取次」をしていたのが羽田正親でした。
吉川平助の後任として熊野山奉行を担当
1589(天正17)年の1月から3月にかけて、藤堂高虎とともに豊臣家の「熊野山奉行」を務めています。「熊野山奉行」の就任は、前年に「材木流用事件」が発覚し、責任者の吉川平助が豊臣秀吉の命で斬首の刑に処されたことに対する処置だったと考えられます。
同じ時期に豊臣秀長は紀伊国熊野地方を完全に掌握したことから、正親は熊野地方北山地域の村落に対して赦免を保証する証文を出しています。
秀長死後の羽田正親の動向
後継者・豊臣秀保にも仕える
1591(天正19)年1月21日、豊臣秀長が大和郡山城で病死。かねてから養嗣子として指名されていた豊臣秀保です。
羽田正親は「大和大納言家」が代替わりしたのちも、秀保の重要な家臣の一人として後陽成天皇の聚楽第行幸(1592年1月)に参列したり、あるいは秀吉からの直接の命令を受け、藤堂高虎や杉若無心とともに紀州熊野地方で材木調達の任にあたっています。
また秀吉の朝鮮出兵(文禄の役)に際して、豊臣秀保は1万の兵で肥前名古屋に参陣しますが、従軍した家臣の中には羽田正親の名前もありました。
羽田正親の最期
豊臣秀保は1595(文禄4)年3月ごろから病気を患うようになり、大和国の十津川で療養をしていましたが、同年4月16日に死去。
このとき「大和大納言家」と言われた豊臣秀長の家系は断絶。残った家臣の多くは秀吉の直臣となる中、羽田正親は豊臣秀次の家老に転じます。正親一人だけが秀吉ではなく、秀次の直臣となった理由は分かっていません。
しかし同年4月、羽田正親は「豊臣秀次切腹事件」に連座したとされ、越前北庄において切腹を命じられ、その生涯を閉じることになりました。
羽田正親 関連記事と参考文献
羽田正親 関連記事
豊臣秀長・豊臣秀保の二代にわたって仕えた羽田正親に関しては以下の記事でも言及しています。合わせて参考にしてください。
羽田正親 参考文献
今回の記事を書くにあたって以下の文献を参考にしました。著者の柴裕之さんと黒田基樹さんは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で時代考証を担当されています。
- 黒田基樹 羽柴秀長とその家臣たち 秀吉兄弟の天下一統を支えた18人 角川選書
- 柴裕之編著「豊臣秀長 (シリーズ・織豊大名の研究)」戎光祥出版
- 黒田基樹 秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治 講談社現代新書