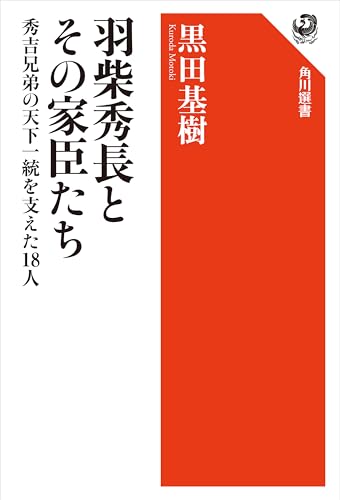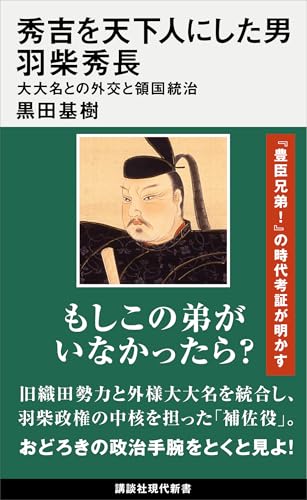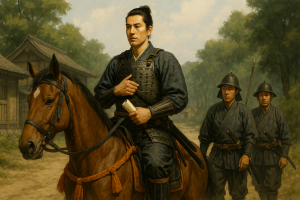福智長通の名前について
福智長通とは
福智長通(ふくちながみち)(生没年不詳)とは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主人公・豊臣秀長(仲野太賀)の家臣の1人です。
福智長通は1587(天正15)年の九州征伐において秀長とともに従軍。
筆頭家老の桑山重晴とともに薩摩の島津義珍(しまづよしたか)(のちの義弘)の「取次(外交や外交事務のこと)」を担当し、戦後の九州国分(きゅうしゅうくにわけ)において日向国における領地配分の実務も担当したことで知られています。
福智長通の名前
福智長通の最初の実名は「通長」でのちに「長通」に改名。
「羽柴秀長とその家臣たち」によると改名は1584(天正12)年にそれまでの「羽柴美濃守長秀」から「羽柴美濃守秀長」に改名したことに伴い、改めて「長」の一字を偏諱として受け取ったことによるものと説明しています。
また1588(天正16)年には秀長の「諸大夫家臣」として朝廷から従五位下三河守に叙任されたことにより、福智長通は受領名として「三河守」と言う名前も持っています。
「諸大夫家臣」とは
「諸大夫家臣」とは公卿である豊臣秀長(従二位権大納言)が宮中に参内するときに御所の中まで随伴することができる家来のことです。
秀長に随伴するほとんどの家来は御所の外までしか警護できないのに対して、「諸大夫家臣」は従五位下の官位を持ち、宮中には昇殿できないものの御所の中に入って警護することが許されていました。
こうした秀長の「諸大夫家臣」には福智長通の他にも、桑山重晴・宇多頼忠(尾藤頼忠)・藤堂高虎・杉若無心・羽田正親らがいました。
福智長通の出自と家族
福智長通の出自
福智長通は生年が不詳であるようにその出自は分かっていません。
史料で福智長通が初めて登場するのは1582(天正10)年のことで、備中吉備津宮宛に出した同年5月13日付の書状において「福智三河守通長」と署名されています。
福智長通の家族
福智長通の家族は嫡男の政直の存在が推定されています。
秀長家臣としての福智長通の動向
島津義珍への降伏勧告と取次
豊臣秀長の家臣として福智長通の名前が頻繁に登場するのは、1586(天正14)年に豊臣秀吉によって始められた九州征伐において、1587(天正15)5月以降のことです。
当時、島津家第16代当主の島津義久は押し寄せる秀吉の大軍勢を目の当たりにして、豊臣家に恭順する意向を示していましたが、日向国を本拠にしていた弟・島津義珍はいまだ抵抗している状況にありました。
以降は「秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治」に記述されている九州征伐後半の様子を年表形式にしたものです。
| 西暦(和暦) | 出来事 |
|---|---|
| 1587(天正15)年5月8日 | 秀長の筆頭家老・桑山重晴が島津義珍(義弘)への降伏勧告 |
| 1587(天正15)年5月13日 | 秀長軍の先陣として桑山重晴・福智長通が日向高原まで進軍。長通は島津義珍に書状を送る |
| 1587(天正15)年5月16日 | 福智長通が桑山重晴に書状を送り、重晴が義珍に渡されれる(内容は義珍が秀吉の元に出頭すること) |
| 1587(天正15)年5月19日 | 島津義珍が秀長の元に出頭。福智長通が取次 |
| 1587(天正15)年5月22日 | 島津義珍が秀吉の元に出頭し、降伏が正式に認められる |
日向国の知行割を担当した福智長通
しかし福智長通にとって大変だったのは、九州征伐ののちに行われた「九州国分(きゅうしゅうくにわけ)」の方でした。
「九州国分」とは九州に在来していた諸大名の所領と豊臣家の直轄地を、豊臣秀吉の名の下に確定させていく知行割のことです。福智長通が知行割の実務を担当した国は九州征伐の経緯から日向国でした。
当時の日向国は島津家以外にも様々な国衆たちが入り乱れた状態で、しかも知行割の地図が豊臣政権側で把握している内容と、島津家側で把握してい地図の内容で食い違っていました。
困難を極める日向国の知行割と激怒する豊臣秀長
特に日向国の真幸院(現在の宮崎県えびの市・小林市・高原町)と、同国の諸県郡(宮崎県宮崎市の一部・都城市・小林市・えびの市・北諸県郡・西諸県郡の全域、東諸県郡の大部分、鹿児島県志布志市・大崎町の全域、鹿児島県曽於市の一部)の解釈を巡り、両者の領域が一致するかしないかで豊臣方と島津方は大いに揉めたようです。
死後に「穏やかな性格」と評された秀長でさえも、途中で何度もブチ切れるほど知行割の作業は難航します。
依然として、島津家による日向「公領」の押領状態は継続していた。島津家は、その釈明として諸県郡は真幸院に一致するとの主張を何度も書状で述べてきて、秀長の側ではその都度、押領停止を求める、という遣り取りが繰り返されていた。この時は、秀長はあらためて秀吉の意向を確認することにし、その結果はこれまでと変わらない内容だったらしい。その時に秀吉から出された決定文書(「御諚の趣墨付を以て」)は残されていないので、具体的なことは確認できできない。おそらく秀長に宛てられたもののため、福智はその写本を作成して、島津家に送ったのだろう。島津家ではそれを、残すべき内容ではなかったため、後世に伝えていないと考えられる。 しかしそのような島津家の態度に、秀長の我慢も限界にきたとみえて、「以ての外御腹立ち」と、激しく怒るようになっていた。
黒田基樹. 秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治 (講談社現代新書) (pp. 95-96). (Function). Kindle Edition.
以下は日向国の国割を巡る豊臣秀長と福智長通の動向を表す年表です。
| 西暦(和暦) | 出来事 |
|---|---|
| 1587(天正15)年5月27日 | 秀長が島津家久に佐土原領の安堵を通知 |
| 1587(天正15)年6月9日 | 桑山重晴・福智長通が人質を差し出していない島津家家臣(伊集院久治・土持綱家など)に人質の提出と城の明け渡しをするよう要請 |
| 1587(天正15)年6月19日 | 秀長が筑前に移動。福智長通は同行。名代として西田等介を日向財部に残留させる |
| 1587(天正15)年6月19日 | 福智長通が島津家家老・上井覚兼に対し、秀長が「白唐犬」と「白野牛」を所望していることを伝える |
| 1587(天正15)年6月21日 | 秀長と福智長通が日向土持に戻る |
| 1587(天正15)年6月29日 | 日向における豊臣家直轄地に島津家家臣による押領が発生。福智長通が島津義珍に対処を要請 |
| 1587(天正15)年7月19日 | 福智長通が島津義珍に対し日向国・真幸院は島津領とするも同国の諸県郡は島津領とは認めないことを説明 |
| 1587(天正15)年7月21日 | 福智長通が島津義珍に対し日向国・真幸院は島津領とするも同国の諸県郡は島津領とは認めないことを再度、書状でもって説明 |
| 1587(天正15)年9月24日 | 福智長通が島津義弘(義珍から改名)に対し日向での横領行為を止めるよう書状で通知(書状には秀長が激怒していることも述べられている) |
| 1588(天正16)年3月6日 | 福智長通が島津家家老・上井覚兼に対し、自身が日向国における豊臣家直轄地の代官になったことを書状で通知 |
| 1588(天正16)年閏5月23日 | 福智長通が島津義弘に対して日向国における押領行為を止めるよう通知(書状には秀長が激怒していることも述べられている) |
結局、こうした日向国での知行割が終了したのは1588(天正16)年8月のことでした。最終的には秀吉の裁定により、真幸院以外にも諸県郡の一部も島津領であると認められたようです。
豊後国・大友吉統の取次
こうした日向国の知行割を行っている間の1588(天正16)年1月ごろ、福智長通は豊前の黒田孝高(官兵衛)と豊後の大友義統との間に発生した国境争いの紛争解決にも関わっています。
ただこのときは福智長通は何らかの普請に従事して九州に下向できなかったため、家臣・伊丹甚太夫らを両者を調停させるために派遣。
このことから福智長通は島津義久だけではなく、疋田就長とともに大友吉統の取次も担当していたことが分かります。
その後の福智長通の動向
福智長通を伝える動向は1591(天正19)年1月10日に行われた千宗易の茶の湯の会に参加していたことが最後になっています。
翌年1592(文禄元)年1月に嫡男と推定される政直が従五位下三河守に叙任されていることから、それまでに死去したと推定されています。
福智長通 関連記事と参考文献
福智長通 関連記事
豊臣秀長の家臣の1人で九州の国割りに携わっていた福智長通に関しては以下の記事でも言及しています。合わせて参考にしてください。
福智長通 参考文献
今回の記事を書くにあたって以下の文献を参考にしました。著者の黒田基樹さんと編著者の柴裕之さんは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で時代考証を担当されています。
- 黒田基樹 羽柴秀長とその家臣たち 秀吉兄弟の天下一統を支えた18人 角川選書
- 黒田基樹 秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治 講談社現代新書
- 柴裕之(編著) 豊臣秀長 (シリーズ・織豊大名の研究) 戎光祥出版