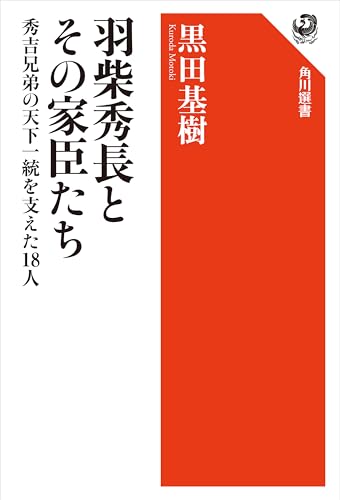横浜良慶の名前について
横浜良慶とは
横浜良慶(よこはまりょうけい)(1549~1596年)は2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主人公・豊臣秀長(仲野太賀)の家臣の1人です。
豊臣秀長の在世中には主に大和国の領国統治を担当し、秀長の死後は豊臣秀吉から指名をされて後継者・豊臣秀保の後見人を務めたことで知られています。
「良慶」は法名
横浜良慶が史料に初めて登場するのは1585(天正13)年7月のことで、このときは「一安(いちあん)」と記されていて、すでに出家していたことがわかります。
「良慶」という下の名前は法名のことで、「多聞院日記」の1587(天正15)年4月朔日の記述に「一庵」が歌を読み「良慶」という名前が添えられていることから来ているものです。
横浜良慶の正確な名前: 「横浜一晏(一庵)大蔵卿法印良慶」
また横浜良慶は「横浜一庵」など別の名前で語られることも多い人物です。
「豊臣秀長 (シリーズ・織豊大名の研究)」によると、1589(天正17)年9月ごろまでは「一庵」で、1590(天正18)年4月から5月までは「一庵法印」、同じ年の7月以降は「一晏法印」と記されていたとあります。
「一庵」という庵号に「法印」がついている理由は、1589(天正17)2月に大蔵卿法印という朝廷の官職が授けられたためです。
これらのことから横浜良慶の名前を正確に呼ぶとすれば「横浜一晏(一庵)大蔵卿法印良慶」ということになるでしょう。
なお横浜良慶の名前について、「横浜一庵光慶」と伝えられることもありますが、こちらの名前は誤伝と考えられています。
横浜良慶の実名について:
横浜良慶の実名についてはよく分かっていません。実名を「正勝」とする説もあるようですが、「羽柴秀長とその家臣たち」ではその説に否定的です。
なお『寛政重修諸家譜』巻六七九「半井系図」では、良慶の実名を「正勝」と伝え、娘が半井利親(一五七九~一六〇三)の子成近(?~一六三九、母は藤堂高虎娘)と結婚し、元和九年(一六二三)にその嫡男の成忠(一六二三~七八)を産んだことを伝えている。しかし良慶の娘とされる人物が、半井成忠を産んだ時の年齢を二〇歳ほどと仮定すると、その生年は慶長九年頃と推定され、それでは良慶はすでに死去したあとのことになり、整合性がない。また結婚した利親の妻を藤堂高虎の娘と伝えているが、藤堂家にはそのことは伝えられていない。したがってそれら半井家の所伝は、そのままには信用できない。
黒田 基樹. 羽柴秀長とその家臣たち 秀吉兄弟の天下一統を支えた18人 (角川選書) (pp. 94-95). (Function). Kindle Edition.
横浜良慶の出自と家族
横浜良慶の出自
横浜良慶の出自はほとんど不明です。
「豊臣秀長 (シリーズ・織豊大名の研究)」によると父親は四郎三郎という人物で、1591(天正19)年正月9日に亡くなったとされていますが、どういう人物であったのか全く分かっていません。
上述した1585(天正13)年の史料では、横浜良慶は豊臣秀吉から秀長家臣の羽田正親とともに紀伊雑賀の兵糧米を四国征伐に従軍している将兵たちに引き渡すよう命じられています。
この史料から横浜良慶が歴史に登場したときには、兵糧米を管理するほど秀長の有力な家臣の1人であったという事実が分かります。
横浜良慶の家族
「羽柴秀長とその家臣たち」では横浜良慶には、妻は前妻と後妻(長連久の娘)の合計2人、子供は男子1人(四郎三郎)・女子3人の合計4人と、妹婿(四木甚左衛門尉)の存在を紹介しています。
一般的に良慶の後継者として横浜民部少輔茂勝の存在が知られています。もっとも茂勝と良慶の年齢は10才程度しか離れておらず、良慶にとって茂勝は弟あるいは甥として考える方が妥当でしょう。
秀長・秀保家臣としての横浜良慶の役割
秀長生前の動向: 大和国の行政や司法を担当
豊臣秀長は1585(天正13)年以降、大和・紀伊・和泉3カ国の領国支配を行うようになります。冒頭で述べた通り、横浜良慶の役割は、秀長の領国のうち大和国の統治でした。
その役割を「羽柴秀長とその家臣たち」ではこのようにまとめています。
そこではおおよそ、大和の領主・寺社に対して知行帳の交付や所領の画定について管轄していたこと、寺社に米などを支給していることから、財政を管轄していたこと、寺社領支配は秀長家臣によっておこなわれていたらしく、寺社への年貢分は秀長から支給する形態になっていて、それを管轄していたとみなされること、郡山町支配にも関わっていたこと、奈良の寺社への祈禱命令とそれへの寄進・布施の給付について差配していたこと、奈良の寺社の修造について差配していたこと、奈良の寺社内部の紛争について調停・裁定していたこと、そして何よりも、秀長に近仕して、奈良の寺社などに秀長からの諸役賦課などに関する命令を伝達する役割を担っていたこと、などをみることができた。
黒田 基樹. 羽柴秀長とその家臣たち 秀吉兄弟の天下一統を支えた18人 (角川選書) (pp. 102-103). (Function). Kindle Edition.
横浜良慶の動向を見ていると、軍事に関わることはほとんどなかった一方で、大和国の行政や司法に関することについて頻繁に登場します。
横浜良慶は財務管理や興福寺や春日大社をはじめとした寺社管理について明るい人材として、秀長から重宝されていたのでしょう。
秀長死後の動向: 豊臣秀保の後見人として筆頭家老の立場に
横浜良慶が大和国で行政手腕を振るっていたものの、秀長の在世中は「大和大納言家」と言われた「豊臣秀長ファミリー」においてどのような立場にあったのかは不明です。
その不明だった立場から横浜良慶を「大和大納言家」で、筆頭家老の座にまで押し上げた出来事が秀長の死です。
1591(天正19)年1月21日、豊臣秀長が大和郡山城で病死。後継者はかねてから養嗣子として指名されていた豊臣秀保です。
秀長が亡くなる直前である1590(天正18)年10月20日の「多聞院日記」には、豊臣秀吉が豊臣秀保の相続に関して以下のような指図を出していたという記述があります。
跡ノ様ハ一晏ニ具ニ被仰渡、和泉ト伊賀トハ余人ニ被遣、紀伊国・当国ハ不替侍従殿被遣間、一晏法印代官トシテ養子ノ侍従ヲ守立ヘキ由被仰了
(現代語訳)
秀長死後のことは一晏法印(横浜良慶)に託しておいた。和泉国と伊賀国は他の者の所領とするが、紀伊国と大和国はそのまま侍従(豊臣秀保)に遣わす。一晏法印を代官として養子の侍従を守り立てるよう申しつけておいた。
秀長が亡くなった直後の1591(天正19)年1月27日の「多聞院日記」の記述でも同じような文章が見られます。
つまり横浜良慶は、秀吉の命令で秀長の後継者・豊臣秀保の後見人として「大和大納言家」の最重要家臣の立場となったことが分ります。
大和郡山城には、かつて「一庵丸」という横浜良慶の名前が付いた区画があったと言われています。良慶が秀保の後見人を務めるほどの重要な家臣であったならば、その名前が付いた建物があったという話も頷けるでしょう。
横浜良慶による大和国の領国統治の動向
「羽柴秀長とその家臣たち 秀吉兄弟の天下一統を支えた18人」などの記述に基づき、横浜良慶による大和国の領国統治についていくつかを年表形式にまとめておきます。
| 西暦(和暦) | 出来事 |
|---|---|
| 1585(天正13)年9月7日 | 添下郡筒井郷(現在の大和郡山市)に奉行・奉公人の不法行為の禁止を通知 |
| 1585(天正13)年9月27日 | 秀長与力の伊藤祐時に1,000石分の知行帳を交付するにあたって郡山城まで受け取りに来るよう通知 |
| 1585(天正13)年11月12日 | 春日大社に米80石を支給 |
| 1586(天正14)年1月13日〜17日 | 興福寺内で起きた紛争を調停 |
| 1586(天正14)年2月24日 | 春日大社の普請奉行として奈良に出張 |
| 1586(天正14)年6月29日 | 秀長の春日大社社参について興福寺の僧侶が出迎えるよう興福寺に通知 |
| 1586(天正14)年9月26日 | 奈良西大寺で山林竹木の伐採を禁止することを保証 |
| 1587(天正15)年2月2日 | 九州征伐にともない奈良の町衆に対して10貫文の夫役納入を通知 |
| 1587(天正15)年8月25日 | 興福寺から「かなふろ・同釜」を受け取り |
| 1588(天正16)年5月4日 | 小堀正次とともに郡山の町衆から1貫文の進上を受ける |
| 1589年(天正17)年12月25日 | 秀長の病気快復の祈祷を奈良の興福寺に依頼 |
| 1590年(天正18)年2月15日 | 秀長の病気快復の祈祷を奈良の興福寺に再度依頼 |
| 1590年(天正18)年7月10日 | 秀長の正妻・慈雲院の命令で奈良の興福寺に秀長の病気快復の祈祷を依頼。同時に南京奉行・井上高清を通じて布施物を受け取るよう通知 |
| 1590年(天正18)年10月4日 | 慈雲院の決裁で寺社領を返還することを奈良の寺社に通知 |
| 1591年(天正19)年1月13日 | 秀長危篤の中、興福寺に大般若経の執行を命令 |
| 1591年(天正19)年1月21日 | 秀長が病死。豊臣秀保の後見人となる |
| 1592(天正20)9月24日 | 京都で「奈良借」に関する帳簿を僧侶たちに筆写させる |
| 1596(文禄5)年7月12日 | 伏見城で城番をしていたところ地震が発生。矢倉で圧死。享年48 |
横浜良慶 関連記事と参考文献
横浜良慶 関連記事
豊臣秀長・豊臣秀保の二代にわたって仕えた横浜良慶に関しては以下の記事でも言及しています。合わせて参考にしてください。
横浜良慶 参考文献
今回の記事を書くにあたって以下の文献を参考にしました。これらの著者のうち柴裕之さんと黒田基樹さんは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で時代考証を担当されています。