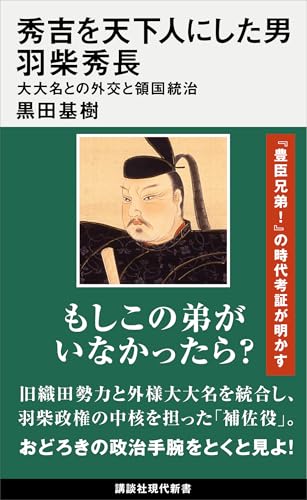奈良借(ならかし)の始まりと顛末
「秀長はケチ」のエピソードと「奈良借」について
2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主人公・豊臣秀長(仲野太賀)に関するエピソードとして、以前「秀長はケチだった」という記事を公開しました。今回の記事ではその記事で触れた豊臣秀長の「奈良貸し」について、詳しく解説いたします。
なお「奈良貸し」とは「ならかし」と読み、本来の漢字表記は「奈良借」です。よって今回の記事では「奈良貸し」ではなく、「奈良借」として表記を統一します。
金子を貸し付けていた秀長と徳政令を出した秀吉
「奈良借」の始まりは1589(天正17)年10月5日、豊臣秀長が奈良の町衆に米1万石を貸し付けたことに始まります。実際には秀長は金子(きんす)1枚を米4石と計算し、金子2,500枚を町衆に対して貸し付けていました。
「多聞院日記」の記述によると、この貸付金は翌年の春に返済されることになっており、実際に元金が返済されたそうです。
ただその後も秀長は奈良の町衆に金子の貸付を行っていて、秀長が1591(天正19)年に亡くなった直後には、金子500枚の貸付残高があったことが確認されています。
しかし金子500枚の貸付は兄・豊臣秀吉の命令によって同年8月に「徳政」、つまり債権が放棄されています。
南京奉行・井上源五による「不正貸付事件」
秀吉が奈良の町衆に対しいわゆる「徳政令」を出したことによって終わったかに見えた奈良借ですが、その後とんでもない経済事件が発覚します。
1592(天正20)年、奈良の町衆が秀吉側近の木下吉隆に対して、秀長・秀保の二代にわたって南京奉行(なんきょうぶぎょう。奈良奉行のこと)として仕えている井上高清(いのうえたかきよ)が不正をしているという直訴状を提出。
その訴えによると、井上源五も奈良の町衆に対して貸付を行っており、その元手は秀長死後に町衆に貸付をしていた500枚の金子であり、しかも利息は金商人(両替商のこと)を通じて井上源五がすべて手にする仕組みとなっているというのです。
奈良の町衆側が勝訴したものの処罰はなし
「図説 豊臣秀長」によると「多聞院日記」の記述に基づき、訴えは町衆側の勝利で終わったと説明しています。
つまり、奈良の町人たちを苦しめていたのは、金商人ではなく、彼らをつかって私腹を肥やしていた井上源五だったことがあぶり出されたわけである。『多聞院日記』九月二十二日条によれば、「直訴のさまは、ことごとく地下人(町人)の勝ち」とあり、また、籠屋に入れられていた町人たちも解放されている。「直訴」はみごとに成功したといえよう。
河内将芳 図説 豊臣秀長――秀吉政権を支えた天下の柱石 戎光祥出版 142ページより引用
しかし、訴えられた井上源五は1600(慶長5)年に亡くなるまで南京奉行として留任。また1592(天正20)年9月、京都ではなぜか豊臣秀保の後見人で筆頭家老の横浜良慶(横浜一庵)が奈良借に関わる帳簿を僧侶たちに筆写させています。
結局、奈良の町衆や金商人たちが一時的に牢に留め置かれる処分を受けただけで、誰も大した処罰を受けることなく、事件は不可解な形で終結を迎えました。
豊臣秀長による奈良借の政策意義
奈良借は奈良への融資だった説
今回の「豊臣秀長と奈良借」をテーマとした記事を書くに当たって参考にした文献は、以下の2冊です。
しかしそれぞれの本で奈良借の意義について解釈が異なります。
黒田基樹さんは「秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治」で「奈良借」についての政策意図については領国が繁栄するための「融資」と捉えいています。
このような金銭貸し付けについて、これまでは利子徴収を目的にした高利貸し活動と理解されることが多い。たしかにその一面もあることを否定しないが、秀長による貸し付けがその死後に秀吉によって破棄されているように、しばしばそうした公金貸し付けは破棄されることも多かった。そのため統治権力による公金貸し付けを高利貸し活動として理解するのでは不十分であり、破棄を想定しての貸し付けであったから、その本質は融資ととらえるのが妥当である。城下の町人・商人に公金を投下し、それにより領国の繁栄を図っていたと理解できる。
黒田基樹. 秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治 (講談社現代新書) (p. 156). (Function). Kindle Edition.
奈良借は朝鮮出兵の軍費調達だった説
一方、河内将芳さんの「図説 豊臣秀長」によると、「奈良借」は豊臣秀吉による朝鮮出兵のための軍費調達のために行われたと解釈ができます。
そのうえ、これには秀吉や秀次もかかわっていたことが知られている。天正二十年十月十日に秀吉から秀次に出された朱印状(『妙法院史料』)に、文禄の役の中で用いる船の費用として「奈良借」で集めた「金銀」もつかうようにとの指示が見いだせるからである。
河内将芳 図説 豊臣秀長――秀吉政権を支えた天下の柱石 戎光祥出版 143ページより引用
奈良借が朝鮮出兵のための軍費をはじめとして、豊臣政権全体で推し進めていた政策のための資金調達策であれば、一奉行に過ぎない井上源五を処罰することはできず、あいまいな形で「事件」の決着をつけざるを得なかったと分析をされています。
奈良借には秀吉か秀長による深い政策意図があった
今回の記事では「秀長はケチ」というイメージに基づいて奈良借の話をしました。
しかし奈良借について専門家の分析を確認すると、「秀長はケチで守銭奴だったから奈良借という法外な高利貸しをしていた」という単純な話ではないことが分かってきました。
奈良借の行われた理由が「奈良への融資」もしくは「朝鮮出兵のための軍費調達」のいずれかだったにせよ、秀長もしくは秀吉による深い政策的な意図があったことが伺えます。
豊臣秀長のエピソード 関連記事
豊臣秀長の逸話・エピソード集
豊臣秀長にまつわる逸話やエピソードは下記の記事でも言及しています。合わせて参考にしてください。