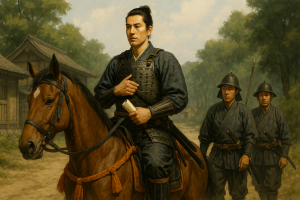宮部継潤の名前について
宮部継潤とは
宮部継潤(みやべけいじゅん)(1528~1599年)とは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の藤吉郎(池松壮亮)(のちの豊臣秀吉)の家臣で、因幡国にあった鳥取城の城主などを歴任しています。
宮部継潤はもともと北近江の大名・浅井長政の家臣で、秀吉の家臣に転じた際に豊臣秀吉・豊臣秀長兄弟の甥にあたる豊臣秀次(当時は次兵衛)を養子にしていたことも有名です。
宮部継潤の名前
宮部継潤は元々、比叡山の僧兵として「善祥坊(ぜんじょうぼう)」を称していたと考えられています。
また1587(天正15)年5月ごろまでには、朝廷から法官位を叙任され「中務卿法印(なかつかさきょうほういん)」や「宮部法印(みやべほういん)」を名乗っています。
宮部継潤の出自と家族
宮部継潤の出自
「豊臣秀次「殺生関白」の悲劇」によると、宮部継潤の父は近江国坂田郡醒井(現在の滋賀県米原市)の在地領主・土肥刑部少輔真舜(しんしゅん)という武士です。
宮部継潤は幼少の頃に比叡山に登り、行栄坊(ぎょうえいぼう)という僧侶について出家。善祥坊(ぜんじょうぼう)を名乗っていました。
その後、善祥坊は比叡山を下りて湯次神社(ゆすぎじんじゃ)の別当であった宮部清潤(せいじゅん)の下につき、名前を「宮部継潤」と改称。
湯次神社の別当とは代々、室町幕府の政所職にある伊勢氏の被官として湯次下荘の荘司を務める者のことです。「豊臣秀吉研究 上」によると、湯次下荘の荘司はいつの間にか「宮部氏」を称して湯次下荘を乗っ取っていたとあります。
そんな宮部氏は宮部城という城も持ち、宮部継潤はやがて浅井長政の重臣に連なるようになりました。
宮部継潤の家族
宮部継潤の実父には土肥刑部少輔真舜、養父には宮部清潤がいたと考えられます。子供は家督を継いだ宮部長房と、後述する養子の宮部吉継(のちの豊臣秀次)がいます。
豊臣秀次の最初の養父となった宮部継潤
宮部継潤が織田家に寝返った時に養子に出された豊臣秀次
宮部継潤は豊臣秀吉の家臣として知られていますが、豊臣秀吉(当時は木下藤吉郎秀吉)に仕えるきっかけとなったのは1571(元亀2)年に浅井方から織田方に寝返ったことです。
このころ秀吉は浅井長政が籠る小谷城の近くに横山城を築いて小谷本城と支城の連携を分断する一方で、姉・瑞竜院日秀(「豊臣兄弟!」のともにあたる女性)と三好吉房(「豊臣兄弟!」の弥助にあたる男性)の長男で、まだ10才にも満たない次兵衛(「豊臣兄弟!」の万丸。のちの豊臣秀次)を宮部継潤の養子に送り込み、浅井家内部の切り崩し工作も行なっていました。
1573(天正元)年に浅井氏が滅亡したのちの論功行賞で、秀吉は継潤の知行を3,000石としています。同じころ弟・木下小一郎長秀が藤堂高虎を召し抱えたときの知行は300石。秀吉は織田方についた宮部継潤をいかに大きく評価していたかが分かります。
つまり秀吉が次兵衛を宮部継潤の養子に出したと言っても、実質的には体の良い「人質」だった可能性は高いでしょう。
この点で、『関白秀次評伝』の著者荒木六之助氏は、「実際には、秀吉の方が頭を下げて、人質がわりにその甥を継潤のもとへ送ったとみるべきである」と述べているが、たしかにその可能性はある。この段階の秀次は、養子といっても、人質のような形で差し出されたとみてもまちがいではないからである。
小和田 哲男. 豊臣秀次 「殺生関白」の悲劇 (PHP新書) (p. 20). (Function). Kindle Edition.
なお宮部家へ養子として送られた次兵衛はのちに元服をして名を「宮部次兵衛尉吉継(みやべじひょうえのじょうよしつぐ)」と改称。「吉継」という名前は「秀吉」と「継潤」の偏諱を一字ずつ合わせてできた名前であると考えられています。
羽柴秀吉家臣としての宮部継潤の活躍
この後、宮部継潤は1577(天正5)年ごろから始まった秀吉の中国攻めに従軍。継潤は主に秀吉の弟・木下小一郎長秀(のちの豊臣秀長)の与力として、但馬・因幡などの山陰方面の戦線に配属。
さらに1580(天正8)年に行われた鳥取城攻めで城が落城したのちは、鳥取城城主として因幡国一国の統治を任されるにまで至ります。
このころ秀吉麾下で継潤の他に一国を任されていたのは、弟・秀長だけでした。宮部継潤の存在は秀吉の家臣としていかに大きかったが分かるでしょう。
ちなみに1582(天正10)年に因幡国の国境に近い但馬国の多伊城が地元の一揆勢によって奪われたとき、城代であった副田甚兵衛尉に代わって城を再奪取したのも宮部継潤の活躍によるものでした。
豊臣秀次との養子縁組を解消したのちの宮部継潤
秀次は宮部継潤から三好康長の養子に「変更」
秀吉家臣として活躍していた宮部継潤ですが、養子・吉継との縁組は解消することになります。
理由は1582(天正10)年に発生した本能寺の変ののちに織田家重臣の間で行われた「清須会議」で、羽柴秀吉を取り巻く政治状況が大きく変わったからです。
当時の宮部吉継の動向として明らかになっているのは1582(天正10)10月22日のことで、秀吉から「宮部吉継」ではなく、「三好孫七郎(みよしまごしちろう)」と記されています。
これは秀次が宮部継潤の養子から、阿波国の三好康長(みよしやすなが)の養嗣子に出されたことを示しています。「孫七郎」とは三好家に因む仮名(けみょう)のことで、実名は「信吉(のぶよし)」です。
「清須会議」では丹波・山城などの畿内2カ国を自分の領国とすることなった秀吉は、畿内に近い四国の阿波を領国とする三好康長と同盟関係を保つために、秀次を宮部家から三好家の養子へと送り込んだのでしょう。
また「清須会議」ののちの羽柴秀吉と宮部継潤の関係を考えると、秀吉の方がすっかり大きくなってしまい、継潤に気を遣う必要もなくなっていたものと推測できます。
なお「豊臣秀次 養子」というテーマについては、下記の記事でも詳しく言及しています。合わせて参考にしてください。
秀次と養子縁組を解消したのちの宮部継潤
秀次が三好家の養子として送られたのちも、羽柴秀吉と宮部継潤の「主従関係」は問題なく続き、継潤は1586(天正14)年の九州征伐において秀長軍の一隊として従軍。
1587(天正15)年5月に日向国で行われた「根白坂の戦い」では、豊臣秀長家臣の藤堂高虎とともに島津勢の島津義珍(しまづよしたか。のちの義弘)を相手に奮戦をしています。
宮部継潤 関連記事と参考文献
宮部継潤 関連記事
大河ドラマ「豊臣兄弟!」ではドンペイさんが宮部継潤役としてキャスティングされています。豊臣秀次との養子関係など、関連記事として以下の記事が参考になります。
宮部継潤 参考文献
今回の記事を書くにあたって以下の文献を参考にしました。これらのうち「羽柴秀吉とその一族」の著者である黒田基樹さんは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で時代考証を担当されています。