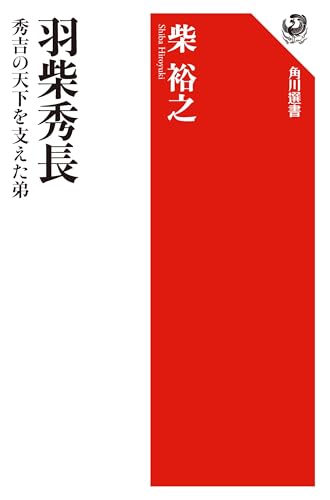秀長の病歴 霍乱(急性胃腸炎)や横根(リンパ節炎)
豊臣秀長 病気の記録
2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主人公・豊臣秀長(仲野太賀)は1591(天正19)年1月21日に大和郡山城で病死します。秀長の死因は「病気」とされているだけで具体的に何の病気に罹って亡くなったのかは、現在のところ判明していません。
しかし大河ドラマ「豊臣兄弟!」の時代考証を担当されている、黒田基樹さんや柴裕之さんの著作物を確認すると、秀長にはいくつかの病歴があったことが分かっています。
1. 1586(天正14)年11月: 「横根(両足の付け根のリンパ節炎)」
黒田基樹さんの著作である「羽柴秀長の生涯」の186ページでは「多聞院日記」の記述に基づき、1586(天正14)年11月ごろ、豊臣秀長は「横根(よこね)」に悩んでいたとあります。「横根」とは両足の付け根のリンパ節が炎症を起こしてしまう症状のこと。
このとき秀長は馬にまたがって乗馬をすることができず、「乗懸馬(のりかけうま)」と言って、人としてではなく「荷物」として馬に乗せられ移動をしていたそうです。
2. 1587(天正15)年末: 「霍乱(下痢や吐き気を伴う急性胃腸炎)」
柴裕之さんが編著となっている「豊臣秀長 (シリーズ・織豊大名の研究)」の282ページによると、1587(天正15)年の年末、秀長は「霍乱(かくらん)」の症状に悩んでいたという記述があります。
「霍乱」とは現代でいう急性胃腸炎のことで、下痢や吐き気などの症状を伴います。この症状を治すために秀長は有馬温泉へ湯治に出かけていたようです。
秀長は過労に伴い免疫力低下をさせていたか
1586〜1587年ごろ、秀長は主に九州征伐とその領土配分である「九州国分」のために、九州と京都を頻繁に往復しています。
その間に秀長は軍事活動・領国支配に加えて、徳川家康・毛利輝元・小早川隆景・大友吉統といった豊臣政権に従属していた大大名に対する「指南(政治や軍事に関する指導)」も行っており、秀長に課せられた仕事は激務だったと考えてよいでしょう。
「横根」や「霍乱」は、ウイルスや細菌が免疫力の低下したリンパ節や胃腸に入りこみ炎症や下痢などの症状を引き起こします。
豊臣秀長の病気とは、過労により全身の免疫力を低下させていたことではないでしょうか。
秀長の病気の治療法: 湯治と祈祷
有馬温泉での湯治
豊臣秀長の病気の症状は1589(天正17)年11月ごろから、次第に重くなっていきます。摂津国有馬の温泉で湯治をした上、京都で療養生活をしていたようです。
そのため豊臣秀吉による小田原征伐には参陣せず、京都で留守居をすることになります。
大和国の寺社を挙げて秀長の快復を祈願
さらに1590(天正18)年に入ると秀長の病気は小康と重篤の状態を繰り返すことに。これに対して正室(正妻)である慈雲院(「豊臣兄弟!」の慶にあたる女性)は興福寺や春日大社など大和国にある寺社に祈祷を依頼。
秀長の了解があったとはいえ、慈雲院は秀長が快復したあかつきに寺社領の返還をすることまで約束しています。
なお慈雲院がいつごろどこの寺社に祈祷を依頼したかは「慈雲院の年表」が参考になります。
豊臣秀長の死因について
豊臣秀長の死去と死因について
有馬温泉への湯治、京都での療養生活、そして寺社での祈祷もむなしく、豊臣秀長は1591(天正19)年1月に具体的な病名は不明のまま死去。享年51。
秀長の跡はあらかじめ養嗣子にしておいた豊臣秀保が継ぐことになります。豊臣秀長の死因については下記の記事でも言及しています。
吉川平助の材木売買事件と秀吉による粛清説
一般的に豊臣秀長の死因は病名の分からない「病死」とされています。それだけに秀長は別の原因で亡くなったのではないかと取り沙汰されることもあります。
その1つが吉川平助による「材木売買事件」です。豊臣秀長の家臣の1人である吉川平助は、1588(天正16)年に紀伊国の熊野で伐採した木材2万本を大坂において不当な高値で売り払ったことで、秀吉の怒りを買い処刑されます。
この事件によって秀長は兄・秀吉の恨みを持たれたと考えることもできます。
しかし、吉川平助は豊臣秀長の家臣として紀伊国・雑賀城の城主を任されていた同時に、秀吉の家臣という一面も持ち合わせ、豊臣家の「山奉行」として紀伊国の材木管理も任されていました。
しかも熊野地方における大量の木材切り出しは、秀吉の直接命令したことによるものです。秀長による命令系統とは違うところで起きた事件であるため、秀吉が秀長を厳しく咎めるというのは筋合いが違う話となるでしょう。
実際、翌年の1589(天正17)年正月に秀長は吉川平助の事件について、秀吉に謝罪するため大坂城へ出向き面会謝絶を喰らいますが、それ以上何か特別に咎められた形跡はありません。
よって「秀長は秀吉によって粛清されて死んだ説」は限りなく可能性が低いと考えられます。
秀長死去の影響
豊臣政権でNo.3の豊臣秀次がNo.2の座に
豊臣一門衆の筆頭大名であった秀長の死によって、それまで秀長に次ぐ地位にあり近江八幡で43万石を領していた豊臣秀次が筆頭大名の地位に引き上げられました。
豊臣秀吉は1590(天正19)年の小田原征伐後に行われた伊達政宗・最上義光たちなど奥羽の大名に対する領土配分いわゆる「奥州仕置」は秀次主導のもとに行われます。
これまでの四国征伐や九州征伐後の領土配分である「四国国分」や「九州国分」は、秀長が実務を担当していました。もし秀長が健在であれば、「奥州仕置」の実務も秀長主導で行われていたでしょう。
秀長の死と朝鮮出兵について
また「秀長が生きていれば秀吉の朝鮮出兵を止められたのではないか」という説もあります。ただ、「豊臣兄弟!」の時代考証担当である柴裕之さんによると、この考え方には否定的です。
「天下一統」を成し遂げた羽柴秀吉は、豊臣政権のもとで統合がなされた日本(便宜上、〝豊臣日本〟とする)と変動する東アジア世界との関係に目を向けていく。これは、「天下一統」が実現したいま、国内だけで完結せず、東アジア世界における〝豊臣日本〟の位置づけが求められたからだ。秀吉は、東アジア世界に〝豊臣日本〟の存在を通じて自らの政治的・軍事的威勢(武威)を示すことを、後世に自身の名声を残す偉業として、強く認識し臨んできた(一五八六年十月十七日付ルイス・フロイス書翰〔『十六・七世紀イエズス会日本報告集』第Ⅲ期第七巻所収〕ほか)。
柴 裕之. 羽柴秀長 秀吉の天下を支えた弟 (角川選書) (pp. 193-194). (Function). Kindle Edition.
豊臣秀吉は、秀長の生前のときから東アジア外交を見据えており、朝鮮が服属しない場合は戦争となることも辞さない考えだったようです。
よって秀長が仮に長生きをしていたとしても、朝鮮出兵は行われていたと考えられます。
豊臣秀長 病気 関連記事と参考資料
豊臣秀長 病気 関連記事
豊臣秀長が何らかの病気で亡くなったことについては下記の記事でも言及しています。
豊臣秀長 病気 参考資料
今回の記事を書くにあたって、大河ドラマ「豊臣兄弟!」で時代考証を担当されている、柴裕之さんと黒田基樹の著作を参考資料としています。