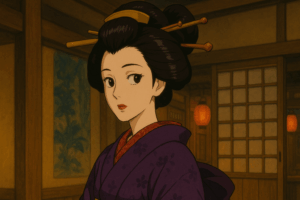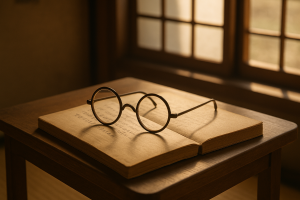江戸・日本橋と蔦屋重三郎の関係
日本橋は江戸の経済・文化の中心地であった
NHKの大河ドラマ「べらぼう」の23話「我こそは江戸一の利者なり」以降のお話で、登場人物たちのセリフから頻繁に「日本橋」というセリフが登場します。
日本橋とは現在の東京都中央区北部にある商業地域・ビジネス街のことですが、「べらぼう」の時代背景となっている江戸時代中期では江戸の経済・文化の中心地でありました。
蔦屋重三郎(横浜流星)に近しい人々は、「ここに本屋を出店しろ」という意味で、日本橋という地名を口にします。
江戸経済の中心地として日本橋
徳川家康が江戸城の築城を始めた16世紀の終わり頃、日本橋地域は江戸湾に非常に近い低湿地帯でした。家康はこの地域を埋立地にし、武士に魚や野菜などの食料を供給する目的で商人を住まわせたことから、経済の中心地としての日本橋の歴史が始まります。
のちに江戸幕府が開かれ(1603年)、三代将軍・徳川家光の治世で参勤交代の制度が確立する頃(1635年)には、1年ごとに江戸屋敷に住まう諸大名たちは、日本橋の商人たちに目を付け、彼らから生活物資を調達するようになりました。
江戸屋敷には諸国からの大名たちだけはなく、人質となった家族・江戸在勤の家来たちも常駐しています。日本橋の商人たちの中から、武家階級の消費によって大きな財をなす豪商が現れ、日本橋は豪商が集まる町となりました。
文化・情報の発信地でもあった日本橋
江戸の富を集めた日本橋は単に経済の中心地にとどまらず、文化や情報が集まる地にもなります。実際、大河ドラマ「べらぼう」に登場する板元たちも日本橋に店を構えていました。
- 書物問屋・須原屋市兵衛(里見浩太朗): 日本橋室町二丁目
- 地本問屋・鶴屋喜右衛門(風間俊介): 日本橋通油町
- 地本問屋・奥村屋源六(関智一): 日本橋通塩町
- 地本問屋・西村屋与八(西村まさ彦):日本橋馬喰町一丁目
彼らはいずれも一流どころの板元で、「日本橋に店を構える」ということ自体が、本屋にとってのステータスとなっていました。
蔦重が日本橋通油町に進出するメリット
1783(天明3)年、蔦屋重三郎は日本橋通油町の丸屋小兵衛から地本問屋の仲間(株仲間)の権利を買い取ります。江戸の外れである吉原の五十間道で営業していた「耕書堂」は、文化の発信地である日本橋に進出するのです。
「耕書堂」が日本橋に進出するメリットは大河ドラマ「べらぼう」で時代考証をされている鈴木俊幸中央大学文学部教授によると、著作の「蔦屋重三郎」でこのように説明されています。
さて、蔦重が丸屋小兵衛から購入したのは不動産だけではなかったはずである。沽券、すなわち営業権ともどもであったと思われる。具体的には明らかにしがたいが、それは主に流通に関わる利権であったろう。問屋同士の交易、また絵草紙屋や行商への卸などに関わる地理的、また営業上の利便を獲得し、蔦重は名実ともに江戸の地本問屋となった。話題性に満ちて、最新のおしゃれ感で抜きん出る日本橋の蔦重店には、多くの新しもの好きの江戸っ子たちが訪れたことであろう。
鈴木俊幸「蔦屋重三郎」平凡社新書 100ページ