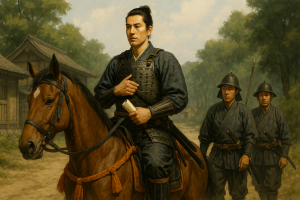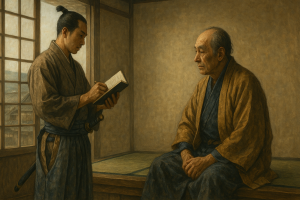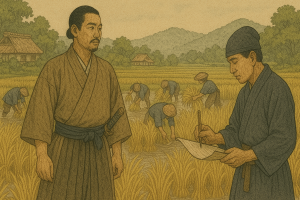北政所と言われた寧々(ねね)の死因
76才のときに病気のために亡くなった高台院
2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で浜辺美波さんが演じる寧々(ねね)、のちに北政所(きたのまんどころ)や高台院(こうだいいん)と言われる女性は1624年(寛永元)年に76才で病気のために死去します。
高台院は、徳川家康や太閤秀吉恩顧の諸大名から非常に尊敬され、関が原の戦いや、大坂両度の陣、大坂落城、秀頼、淀殿の死亡、豊臣家滅亡などという数々の大事を常に静観しながら、その余生を安らかに過ごし、家康からは河内の内で化粧料として一万三千石を与えられ、寛永元年(一六二四)九月六日、七十六歳で病死している。遺骸は高台寺内の豊臣廟の下に葬られた。
桑田 忠親. 豊臣秀吉研究 下 角川選書クラシックス (p. 357). (Function). Kindle Edition.
上記の文章は豊臣秀吉研究の第一人者として知られる國學院大学 故・桑田忠親名誉教授の著作「豊臣秀吉研究 下」から引用したものです。
この本によると高台院の死因は「病死」とだけ書かれていて、高台院は具体的にどんな病気に罹って亡くなったかについては言及されていません。
北政所・高台院の名前について
大河ドラマ「豊臣兄弟!」に出演する浜辺美波さんは、藤吉郎(池松壮亮)(のちの豊臣秀吉)の妻の寧々(ねね)として紹介されています。
豊臣秀吉の正妻。秀吉が関白に就任したのちは北政所(きたのまんどころ)と称される。
負けず嫌いの性格で、夫の秀吉とともに出世街道を駆け抜ける。
やがて庶民の娘から“戦国のファーストレディ”へと昇りつめる。
寧々(ねね)は1585(天正13)年7月11日に豊臣秀吉が関白に任官したことによって、「北政所」として敬称されるようになります。
さらに「高台院」という名前は朝廷から勅許を得た院号であり、1603(慶長8)年11月以降にこの号を使って手紙の署名を行なっています。
そのため晩年の寧々について「高台院」という院号を使って呼ばれることが一般的です。
高台院 晩年のエピソード 2選
甥・木下勝俊に宛てた手紙でわかる高台院と家康の仲
「高台院」と号するようになった寧々は、自分の身内をはじめとして、皇族・公卿・僧侶・武士・医者など様々な人たちと手紙のやり取りをしていたことが明らかになっています。
一ふで申まいらせ候。さやうに候へば、ひら野之事、としよりどもにまかせ、だいくはん入ずに、申付られ候べく候。米にねんを入、年々あげ候弐百石も、又、御はらいなども、ひらのゝ大郎びやうへに、よくしてをき候へ。用しだいに、つかい候はんよし、かたく申付らるべく候。そのため申候。以上。
慶拾五年
六月廿日(黒印)長せう
まいる桑田 忠親. 豊臣秀吉研究 下 角川選書クラシックス (pp. 351-352). (Function). Kindle Edition.
【現代語訳】
さて、平野(ひらの)の件については、年寄りたち(古くからの家臣・村役人など)に任せ、
代官などは入れずに、その者たちに申し付けるようにしてください。
毎年の年貢として上げている米二百石のことや、
その他の御払い(=上納金・奉納金など)についても、
平野の大郎兵衛(ひらののだいろうびょう)にきちんと引き継いでおきなさい。
必要に応じて使うよう、固く申し付けておくように。
以上、そのために申し上げました。
1610(慶長15)年 6月20日(黒印)
長嘯子
手紙の背景
上記の手紙はその1つで自分の兄・木下家定の息子、つまり甥の木下勝俊に宛てたものです。
文中にある「平野」とは摂津国東成郡平野荘(現在の大阪市平野区のあたり)のことで、当時は高台院が勝俊に与えた所領でした。
平野荘には末吉増重(大郎兵衛のこと)をはじめとした村役人たちがいたにもかかわらず、勝俊は年貢徴収のために代官を別途置こうとしていたようです。
高台院は代官を置くことについて勝俊を諌め、年貢徴収のことは末吉増重らに任せなさいと伝えようとしています。
必ずしも徳川家康に従っていたわけではなかった高台院
このころ木下勝俊は浪人をしており、「長せう(長嘯子。ちょうしょうし)」を名乗っていました。
勝俊の父・木下家定は1600(慶長5)年の関ヶ原の戦いののち、備中国足守2万石を所領としていました。1608(慶長8)年に家定が病気で亡くなると、徳川家康はその遺領を勝俊と弟の利房と分けて相続するように高台院(当時は北政所)に指示。
ところが高台院は家康の命令には従わず、兄の遺領を全て勝俊に相続させてしまいます。このため家康は大層怒り、備中足守2万石は没収。勝俊は浪人をすることに。
NHKの大河ドラマでは、よく秀吉の正妻であった高台院は家康と誼を通じているような場面が描かれます。
しかしこうした高台院の晩年を知ると、高台院は必ずしも家康の言うことに何でもかんでも従っていた訳ではなかったことが分かるでしょう。
徳川秀忠を通じて徳川家全体とは誼みを通じていた高台院
家康のやることに全面的に賛成していた訳でなかった高台院ですが、一方ではその息子である徳川秀忠とは誼みを通じ、徳川家全体とは友好関係を築いていたこともわかっています。
返々、あつき時分、みな〳〵も、御しんらうどもにて候はんと、をしはかりまいらせ候。我身ににあひ候御よふの事候はゞ、うけ給候べく候。かしく。返々、御とうりうの中には、御けもじにて候べく候。かしく。 将ぐんさま御上らく、数々めでたく思ひまいらせ候。万よきやうに御とりなし、たのみ〳〵入まいらせ候。まづ〳〵、うつくしくも御入候はねども、御かたびら十まいらせ候。あせとりにめし候はゞ、御うれしく思ひまいらせ候べく候。かしく。
高台院
いたみ
ね
きの介殿
桑田 忠親. 豊臣秀吉研究 下 角川選書クラシックス (p. 353). (Function). Kindle Edition.
【現代語訳】
重ねて申し上げます。
暑い時期のことゆえ、皆々さまもお疲れのこととお察しいたします。
もしも、私のような者でお役に立てるようなご用向きがございましたら、ぜひお申し付けくださいませ。
つつしんで申し上げます。
重ねて申し上げますが、
ご道中の間は、どうぞご自愛のうえ、御けもじ(ご精進=粗食を召し上がる)でお過ごしくださいませ。
つつしんで申し上げます。
将軍様のご上洛のこと、誠にめでたく思っております。
何事もつつがなく進みますよう、心よりお祈り申し上げます。
ささやかではございますが、まだ出来映えは十分とは申せませんが、
帷子(かたびら。麻の単衣)を10枚お納めいたします。
汗をお拭きになる際にでもお使いいただければ、これほど嬉しいことはございません。
つつしんで申し上げます。
高台院
伊丹喜之助康勝 殿
寧々(ねね)
手紙の背景
この手紙の背景は1605(慶長10)年5月ごろに、徳川秀忠の家臣・伊丹喜之助康勝(いたみきのすけやすかつ)に宛てて出されたものです。
すでに徳川幕府の二代将軍に就任していた徳川秀忠の上洛を祝し、麻でできた単衣を贈ったことを喜之助に報告しています。
家康の言うことをそのまま鵜呑みにして従わないこともあれば、その一方ではすでに世は徳川の治世に移っていること敏感に感じ、徳川家との誼みはしっかり保っていたようです。
こうした残された手紙の存在から、晩年の高台院は優れた処世術を持つ女性であったと言えるでしょう。
高台院 関連記事と参考文献
高台院 関連記事
のちに北政所や高台院と言われる豊臣秀吉の正妻・寧々(ねね)と言われる女性については下記でも言及しています。
- ねね(寧々)家系図 北政所 高台院の家族 豊臣兄弟! 浜辺美波
- 豊臣兄弟! 寧々(ねね)豊臣秀吉の正室(正妻)(浜辺美波)
- 寧々(ねね) 子供 豊臣秀吉との子供 養子の秀勝・ごう・小姫・秀俊
- 寧々(ねね) 性格 織田信長とねねの関係 高台院の性格
高台院 参考文献
今回の記事は下記の文献を参考としています。