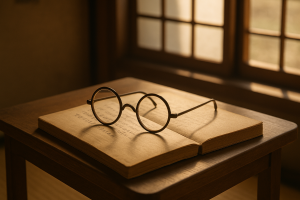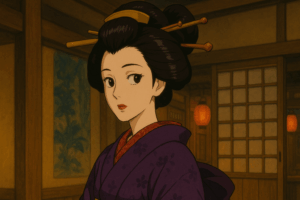蔦重の実母・つよとは
「べらぼう」の「つよ」とは広瀬津与
NHKの2025年大河ドラマ「べらぼう」で、高岡早紀さん扮する「つよ」とは蔦屋重三郎の実母のことです。
つよは蔦屋重三郎の菩提寺である浅草・正法寺に遺されている「実母顕彰の碑文」から、「広瀬津与(ひろせつよ)」という女性であることが分かっています。
大河ドラマ「べらぼう」 つよの役柄
大河ドラマ「べらぼう」では高岡早紀さんが扮するつよの役柄を以下のように説明しています。
蔦重(横浜流星)が7歳の時に離縁し、蔦重をおいて去っていった実の母親。髪結の仕事をしていたこともあり、人たらし。対話力にはたけており、蔦重の耕書堂の商売に一役買う。
大河ドラマ「べらぼう」いざ、日本橋へ!高岡早紀・水樹奈々・高橋英樹ほか 出演決定 – 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」 – NHK
NHKの説明の中で「7歳の時に離縁し」と「蔦重の耕書堂の商売に一役買う」という箇所については、史実に基づいた設定であると考えられます。
というのも蔦屋重三郎が大田南畝(桐谷健太)に依頼してつよを讃えた碑文の中に、その事実が刻まれているからです。
蔦屋重三郎の実母、広瀬津与とはどんな女性だったのか?
「実母顕彰の碑文」から見る広瀬津与
以下は正法寺に遺されている「実母顕彰の碑文」の内容と、その碑文を現代語訳にしたものです。漢文による文章は「新版 蔦屋重三郎」から引用しています。
「実母顕彰の碑文」の原文
広瀬氏者書肆耕書堂母也 諱津与江戸人 帰尾陽人丸山氏 生柯理而出 柯理幼冒喜多川氏称蔦屋重三郎 其居近倡門 天明三年癸卯九月移居城東通油町而開一書肆 競刻快書大行 都下之好稗史者皆称耕書堂 寛政四年壬子十月二十六日広瀬氏病死葬城北正法寺 癸丑二月柯理来請曰小人七歳離母而復合以有今日 願得片言志於墓以報劬労 予曰吾見人破産而入曲中者矣未聞出曲中而起業者也 予之志不渝則蓋足以観母氏之遺教矣 銘曰小説九百母徳可摘 寛政癸丑暮春南畝
松木寛「新版 蔦屋重三郎」講談社学術文庫 51ページ
「実母顕彰の碑文」の現代語訳
広瀬氏は、書店「耕書堂」の主人・蔦屋重三郎の母である。
名は津与といい、江戸の人である。
もともとは尾張国(今の名古屋周辺)の丸山氏に嫁ぎ、その家にて蔦屋重三郎を産んだ。
重三郎(幼名・柯理)は幼くして喜多川氏を名乗るようになり、「蔦屋重三郎」と称した。
彼は、当初は江戸の遊女街の近くに住んでいたが、
天明3年(1783年)9月、江戸の城東・通油町に転居し、そこで書店を開業した。
当時、競って出版される娯楽本(洒落本・黄表紙など)は大人気となり、
江戸でこうした読み物を好む者は皆、耕書堂を名店と称えた。
寛政4年(1792年)10月26日、広瀬氏(津与)は病気で亡くなり、
城北の正法寺に葬られた。
翌年の2月、重三郎(柯理)は寺に参り、こう願い出た。
「私は7歳で母と別れ、のちに再び会って、今日の私があります。
どうか母の墓に、少しでも私の感謝の気持ちを言葉にして刻ませてください。
母のご苦労に報いたいのです。」
私は(それを聞いて)こう言った。
「私は、破産して遊女の世界に身を落とした人は見たことがあるが、
そのような世界から身を起こして成功した人は見たことがない。
あなたの志が変わらず、ここまで来たのは、まさに母の教えのたまものだろう。」
銘文:
「九百冊の小説を出した人、その陰には母の徳があった」
寛政5年(1793年)晩春 南畝(大田南畝のこと)
父・丸山重助の碑文はない
浅草・正法寺にある「実母顕彰の碑文」の横には、蔦屋重三郎の功績を称えた「喜多川柯理墓碣銘(きたがわからまるぼけつめい)」が刻まれています。
しかし、蔦屋重三郎の父である丸山重助にはこうした碑文はなく、どういった人物であったのか「実母顕彰の碑文」に刻まれている内容以外のことは分かっていません。
蔦屋重三郎にとって格別な存在だった広瀬津与
これらのことから蔦屋重三郎にとって、実母の広瀬津与は特別な存在であったことがうかがえます。上述した「新版 蔦屋重三郎」では、広瀬津与について以下のような人物であったと推測しています。
重三郎にとって、母親津与は格別な存在であったようだ。重三郎が南畝に依頼して、母親の遺徳を讃える碑文を作ったこと自体、重三郎の津与に対する心の象徴である。碑文の中で南畝は、重三郎を成功に導いた彼の堅固な意志は、想うに母親の教育の賜物だろうとの趣旨のことを述べ、幼年期における人間形成の過程で、津与が重三郎に及ぼした影響力の甚大さを示唆している。これから推測するに、強い意志をもった人間となることの必要性を諄々と説きながら、我が子の大成を願いつつ、彼女は重三郎を育てていったと思われる。
松木寛「新版 蔦屋重三郎」講談社学術文庫 22ページから23ページ
NHKはつよの役柄を「蔦重の耕書堂の商売に一役買う」と簡単に説明しています。しかしこの簡単な一言こそが大河ドラマ「べらぼう」における、つよの見せ場であると考えられるでしょう。